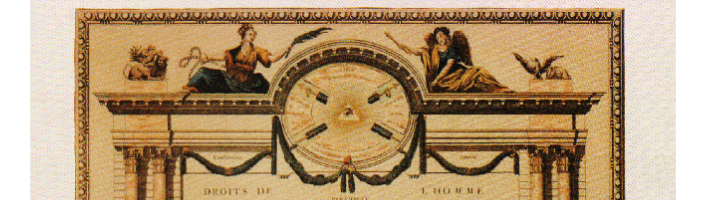「教育権」の判例:旭川学力テスト事件
教育を受ける権利と教育権―旭川学力テスト事件―
茨城大学 中野雅紀
最高裁昭和51年5月21日大法廷判決
事件名 昭和43年(あ)第1614号建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件
刑集第30巻5号615頁、判時814号33頁、判タ336号138頁
概要 本件は当時、家永教科書裁判を契機として、国家教育権説と国民教育権説の鋭い対立関係にあったが、最高裁判所がそのどちらも「極端かつ一方的であるとしてそのいずれをも全面的に採用することはではない」という立場を示し、藤井樹也氏にならえば「国家=悪、国民=善」という二元的対立から離れ、ひいては教育権概念の多義的概念化を押し進めることになった判決である。事件の内容は、昭和36年に施行された全国中学生一斉学力調査を阻止するために、労組役員Yらがおこなった行為が建造物侵入、公務執行妨害、共同暴行罪として起訴されたというものである。
事実関係 本件を理解するには、まずこの全国学力試験を説明しておく必要性があろう。本試験は戦後初期の学力低下をめぐる議論を背景として、当時の文部省により「学習指導要領その他の教育条件の整備改善に寄与しようという目的で」昭和31年に開始され以後11年間にわたって毎年実施されたものである。やがてこの試験は昭和36年に中学校の悉皆調査に切り替えられることになったが、この調査切り替えにより当初から反対していた日教組の反対運動がピークに達し、そのなかで北海道教職員組合他の労働組合役員であるXらがその実施を阻止する際に建造物侵入等の犯罪を行ったとして起訴された刑事事件である。具体的には、旭川市永山中学校で実施予定の全国中学一斉学力調査を阻止するために、上述のXらが十数名の説得隊員らと共に同校舎に侵入し、それに対して退去要請を行った同中学校長Yの退去命令に応じなかったばかりか、XらがYらに暴行脅迫を加えたために建造物侵入、暴行及び公務執行妨害で起訴された事件である。第1審の旭川地判昭和41年5月25日は、全国中学一斉学力調査は違法であり、かつその違法性がはなはだしく重大であるとして公務執行妨害罪の成立は否定したが、建造物侵入と共同暴行罪の成立を認め、Xらのうち2名に罰金刑、他の2名に執行猶予付きの懲役刑を言い渡した。また、第2審の札幌高裁昭和43年6月26日も第1審の判断を支持して、各控訴を棄却した。それに対して、Xらは最高裁判所に上告した。
判決要旨 一部上告棄却、一部破棄自判。「わが国の法制上子どもの教育の内容を決定する権限が誰に帰属するとされているのかについては、二つの極端に対立する(国家教育権説と国民教育権説)があるが」、それらは「いずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用することはできない。」憲法26条の「規定の背後には、国民各自が、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利を有すること、特に、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。」しかしこのことから「教育の内容及び方法を、誰がいかにして決定すべく、また、決定することができるかという問題に対する一定の結論は、当然には導き出されない。」憲法23条の保障する学問の自由は「知識の伝達と能力の開発を主とする普通教育の場においても、例えば教師が公権力によって特定の意見のみを教授することを強制されないという意味において、また、子どもの教育との間の直接の人格的接触を通じ、その個性に応じて行われなければならないという本質的要請に照らし、教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の教授の自由が保障されることを肯定できないではない。」しかし、「児童生徒に……批判能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有すことを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかるうえ上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師の完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない。」「憲法の次元における……教育権帰属問題の解釈としては……関係者らのそれぞれの主張によって立つ憲法上の根拠に照らして各主張の妥当すべき範囲を確定するのが、最も合理的な解釈というべきである。」「それ以外の領域においては……国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立、実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、あるいは子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権限を有する。」
コメント 本件の最大の論点は、それまでの教育決定権の所在について闘わされてきた「国家教育権説」と「国民教育権説」の二つの見解を取り上げて、これらの見解を「いずれも極端かつ一方的であり、そのいずれをも全面的に採用できない」とし、憲法26条の「教育を受ける権利」を子どもの「学習権」を中心に捉え直し、また憲法23条に基づいて普通教育における教師の教育の自由を一定の範囲で承認しながらも、その一方で国家の教育内容決定権を肯定したことである。
以上のように、「国家教育権説」も「国民教育権説」も極端かつ一方的で全面的に採用できないことから、親・私学・教師・国家などの各主体がそれぞれ一定の範囲で教育決定権を有することとなり二者択一的な判断は行われなくなっている。なるほど、家永第二次教科書訴訟地裁判決のように「国家教育権説」を採って「国家が教育内容に介入することは許されない」ことはもっともらしく聞こえるが、では「国民教育権説」を採用しても藤井氏の指摘する以下の問題が残ろう。すなわち、この説には、「親、教師、教科書執筆者など多様な主体が『国民』概念に、教育を受ける権利、教育を行う権利、教育内容を決める権限などの種々の権利・権限が『教育権』概念にそれぞれ包括され『国民の教育権』概念が多義的・曖昧になる」という危険性がある。また、国民自体が多種多様であるために、国家以外の主体すべてが国家対抗的関係にあるという単純な図式が当てはまらなくなった。
その他に、「教育を受ける権利」内の教育を受ける権利、教育を行う権利、教育内容を決める権限の錯綜、あるいは教師の「教授の自由」を憲法23条の学問の自由から基礎付けているが、その限界をどこに置くかという問題等が残される。後者については、伝習館高校事件の箇所を参照されたい。
ステップアップ 百選Ⅰ五版147事件(米沢公一)、佐藤・土井編『判例講義 憲法Ⅰ』143事件(藤井樹拓)、野坂泰司『憲法の基本判例を読み直す』(有斐閣、2011年)第20章