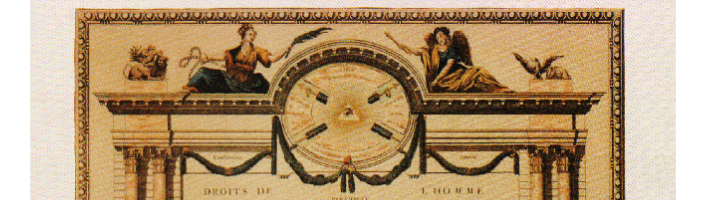|
|
14日、81歳で亡くなったロナルド・ドウォーキンは現代の法哲学・政治哲学界に屹立(きつりつ)する巨人である。革新的かつ論争的なスタイルで英米圏のリベラルな思潮を主導し、合衆国最高裁の動向にも大きな影響を与えた。
アイザイア・バーリンやジョン・ロールズ等のリベラリズムの主流は、価値の多元性を強調し、多様な世界観の公平な共存を提唱する。これに対してドウォーキンは、価値の世界は全体として整合していると言う。自由と平等、社会生活の道徳と個人的倫理とは衝突しない。何が責任ある態度か、何が正しい政策か、すばらしい人生とは何かは、すべて矛盾なく支え合っている。人が自分の生を意味あるものとして生きるには、すべての価値は統一された姿で捉えられなければならない。
1977年に出版された最初の論文集『権利論』は、支配的思想であった法実証主義と功利主義を根底的レベルで批判した。法実証主義によれば、法は社会的事実である。議会がある時点で法律を制定したという事実が肝心であり、内容の道徳的な正しさはそれが法か否かとは関係がない。
一方、ドウォーキンは、何が法かは道徳と切り離して判断できないと言う。法令や先例は互いに衝突する。条文通りでは非常識な結論が生まれることもある。そのとき裁判官は、法令や先例を全体として整合的に、説得的に説明する道徳原理の体系を構築し、それに基づいて具体の事案に適切な答えを与える。法と道徳は不可分である。
功利主義は社会全体の幸福を最大化するか否かが、善悪の唯一の基準だとする。これでは、少数の人々を虐待することで多くの人々が幸福になる政策が正当化されかねない。ドウォーキンは、功利主義も一人一人の幸福を平等に扱うという前提に立つはずだと言う。平等な存在としての個人の尊厳を損なう政策は、この功利主義の前提に反する。個人を平等な存在として扱うよう求める権利、生き方を自ら決め、責任をとる存在として扱うよう求める権利は、功利計算に基づく政策決定を覆す「切り札」となる。
筆者はロンドン大学のゼミや国際学会等で、謦咳(けいがい)に接する機会があったが、深遠な問題を明晰(めいせき)に、ユーモアを交えながら分かりやすく解説する姿は晩年に至るまで変わることはなかった。最後の著書『ハリネズミの正義』の末尾で、彼は生と死について語る。善き生は、人並み優れた業績を残す生ではない。芸術作品の価値もその創造の過程にこそある。我々はむしろ「善く生きる」ことを目指すべきである。尊厳なき生は、一瞬で消える。しかし他者を尊重し、自らも善く生きるならば、「我々の生を宇宙の膨大な砂粒の中の小さなダイヤモンドとすることができる」。東欧からの移民の子として生まれ、母子家庭で育ったドウォーキンは、輝いていた。