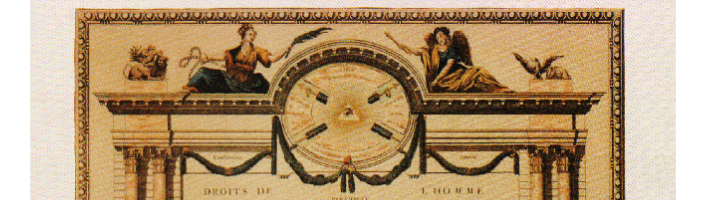キルケゴールとデュルケイムの思想をレポートにまとめる
9月1日の備忘録。
あっという間に、怒涛の8月が過ぎ去り、9月に突入してしまった。しかも、このブログを読んでいる訪問者からすると、お前はここ1週間遊んでいるだけなのかと勘違いされてしまう可能性がある。そこで、今日はわたしも勉強しているのだということをこのブログに書き込むことにしよう。
まず、午前中は前日まで仕上げていたキルケゴールの『全集第6巻』の要約に続いて、キルケゴールの「新たなる価値」の創造におけるキーワードである「アイロニー」と「ユーモア」の批判的検討を加え、まとめる作業をおこなう。今回の勉強で、キルケゴールを読み返してみてなかなか面白い思想家であることを再確認した。といっても、これまで『死にいたる病』しか読んでないわたしがこんなことを言える資格があるのかどうかは、極めて疑わしいのであるが。
午後は、デュルケームの『自殺論』の要約を行い、彼のアノミー論を批判的検討を加え、まとめる作業を加える。ところで、アノミーといえばわたしにとっては小学生高学年から中学生にかけて集中して読んだ山本七平氏や小室直樹氏の「空気」、「ニーマ」そして「アノミー」ということになる。これに近いことを近時使っているのが、TPP亡国論の主要論者である中野剛志氏ということになろうか。そういえば、氏の著作の注には英文ではあるがデュルケムの著作が引用されていたなと思う。
現代倫理学の諸問題
「第三部・Ⅳ・四、新しい価値の創造という問題について」
一.問題の所在
これからの生存そのものにかかわる危機に対処するため、「人類が今までの、ものの見方や考え方も含めた生き方やその道筋を、即ち、在り方そのものを、根本から反省し問い直さなければならない状況に追い込まれている。」その危機的状況に直面して、「今まで人類が共通にそれにのっとりそれにおいて生きてきた価値の体系に対して、これからは、それとは全く異なった全く新しい価値の体系に生きなければならないと考えることは、……至極くもっともなことであ」り、このことを「新しい価値の創造」の問題という(大谷・池上・小松共著『現代倫理学の諸問題』(慶應大学出版、2012年)284頁)。ところで、筆者の大谷愛人が指摘するように以下の点でこの問題は一つの大きな事実とぶつかる。曰く、「価値の問題をそのような更に深い根源的で自由な立場から根本的に考えようとするとき、われわれは、……価値の研究は永い歴史をもっているにも拘らず、価値の問題はまだ一度も根本から取りあげられたことがないと言ってもよいような事実である」(大谷・前掲書285頁)。倫理学では価値に関し、「それは、……逆説の問題が殆ど主題化されたためしがないという事実」を意味する(大谷・前掲書285頁)。ちなみに、逆説の問題とは、大谷によれば以下のように説明される。曰く、「価値の問題は、この『逆説』との出会いを通じてという仕方以外では、問題にしえないものだということを強調するものである。どんな科学的情報もそれ自体としては、事実命題であるから、それは、精神的意識……において受けとめられる性質のものとしての命題であるから、それはつねに『反省的思惟』を通じて訴えられてくるものとしてある。そこでこの反省的思惟において、この命題は本質的にまず逆説という形式で、つまり、自らの善や正直さへの疑いがますます大きくなる仕方で、姿を現してくるのである」(大谷・前掲書281頁)。この倫理学において価値論が主題として殆どとりあげられてこなかった学説状況に対して、大谷はキルケゴールを手掛かりに「価値の逆説」の問題を解明しようとする。そこで利用されるのが、キルケゴールのアイロニーとユーモアである。果たして、この逆説の問題を大谷、ないしキルケゴールは解明しているのであろうか。それが、この課題でのテーマである。
二.大谷愛人によるキルケゴールの「アイロニー」と「ユーモア」の説明
1.まず、大谷にとってキルケゴールの「アイロニー」とはどのように説明されるのかを観ていくことにする。大谷によれば、古代ギリシアのソクラテス、ロマン主義時代のヘーゲル「のあとをうけてアイロニーの問題を主題的にとりあげたのが、……キルケゴールであり」、彼は「アイロニーを、世界史の中で主体性が登場してくるときの出現形態とし……、つまり、話法の形式としてではなく、実存の形式としてとらえたのである。(彼の)アイロニー理解の根本は、ソクラテスの話法だけではなく、国家や人々やそして歴史の中におけるソクラテスの立場そのものを意味するものであり、つまり、ソクラテスの立場そのものがアイロニーなのだとなした。こうして(彼は)、ソクラテスのアイロニーをもって世界史に主体性が登場してくる最初の出現形態とし、主体性の第二の主体性をロマンティシュ・イロニーにみ、そして更に、主体性の第三の出現形態を自分自身であるとそっと自覚していた。しかし、彼の立場は、アイロニーの立場が最も徹底化されたものとして本質的にはユーモアの立場になっていた。……とにかく、彼は、そのような自覚のもとにアイロニーを主題的に究明したのである。そして彼は歴史上、アイロニーの概念を主題的に究明した最初の人物と言えよう」(大谷・前掲書286-287頁)。
では、キルケゴールのこの究明の成果とは何か。これも大谷の説明を借りるならば、以下のように要約できよう。曰く、「アイロニーについての彼の考え方の決定的な特徴は、アイロニーを、話法の形式としてではなく、実存の形式として、即ち、実存の一つの立場を意味するものとしてとらえ、そのアイロニーの立場を、いくつかの可能な実存のなかにはっきりと位置づけた点にあるといえよう。キルケゴールにおいては、アイロニーの立場は、美的実存、即ち、実存の倫理的段階……との間の境界線上にある立場として位置づけられている。従ってその立場において発現している『アイロニー』には、現実全体へとべったりくっついた直接的な在り方の自己倒壊とその否定のなかに反射的にほのみえる『イデー』へのかすかな指標とが含まれている。要するにこの『アイロニー』は『善』とされる『イデー』の最初の目くばせを含んでいるのである」(大谷・前掲書287-288頁)。
このような「アイロニー」の立場は、次のような構造を内蔵することになる。「純粋の『イデ゜ー』を志向する自我の目には、つねに『現実』はその『イデー』を裏切った形式のものとして、つまり逆さになったものとして映るので、その自我は、自分にそのような『現実』にべったり直接化する在り方を拒絶しようとする。つまり、自我は、『現実』全体に対して否定的にかかわることになる。その『否定的なかかわり方』はいろいろあるが、それらのうちの一つに『アイロニー』の立場があるわけである。というのは、一般的立場では『イデー』は単に客観的概念としてだけ把握されているのであり、そのような枠に入った『客観的概念』と『現実』との関係が個々の人間の頭上を超えて客観的、概念的に問題になるにすぎないが、『アイロニー』の立場においては、自我は、主体として、全体性を介して『イデー』を求めるので、そこでは自我の在り方の全体が前者の場合とは全く別様の意味合いと仕方のもとで展開されるのであり、従って『現実』全体への対応としての否定の営みも全く別様に展開されるのである」(大谷・前掲書288頁)>
以上のようにアイロニーの立場の構造を理解するならば、その特徴として以下の三点が挙げられることとなる。ここでも、大谷の説明を借りつつその特徴を挙げることにする。
「第一に、アイロニーは、無限にして絶対的な否定性の立場である。それは『現実』全体が主体に対してもとうとする支配に対する、即ち『絶対性』に対する否定性である。
第二に、アイロニーは、主体性の規定であり、主体が否定的自由を、即ち、『現実』全体を否定することによってえられる自由を、たのしむ立場である。
第三に、アイロニーは、優越性を本質としており、それは優越的な、或は、優越感的な笑いの立場である。
アイロニーの本質的特徴は、以上の三つにまとめることができる。要するにアイロニーの立場とは、自我が、主体的になろうとして、現実全体に対して優越的な笑いの立場から、その現実全体に『むなしさ』を無限にして絶対的に否定することによって、自らの主体性、主体的自由をたのしむ立場、ということができよう」(大谷・前掲書289-290頁)。
なお、この特徴から問いが発生するが、このレポートの論文構成上、それは批判的吟味として「三」の箇所で検討する。
2.続けて、大谷によってキルケゴールの「ユーモア」とはどのようにせつめいされるのかを観ていくことにする。大谷によれば、ユーモアとは以下のものである。曰く、「アイロニーの立場は、現実全体を笑っているつもりではいるが自分自身に対してだけは笑わないことによって、大きな虚構のうちにあることを暴露したが、この自分自身をも含めて現実全体を笑うときはじめて現実全体を笑ったといえるわけであるが、それをなすためには、アイロニーの立場をそれ自らの方向に遡及的に更に徹底化したところの、より深いより高次の立場へと至ることが必要である。それがユーモアの立場であるが、これについてキルケゴールは次のように言っている『ユーモアとは、その振動が最大限にまで徹底的に行われたアイロニーのことである』と。ユーモアの立場は、アイロニーの否定の働きと笑いがアイロニーそれ自身に遡及してくることを認める立場である。キルケゴールは言う『ユーモアの人は、体系哲学が決して体系において計ることのできないものに眼をむける……ユーモアの人は充実においても生きようとするのである。従って彼は、もっとも幸福な気分で語ったものでも、それが不断にどんなに多く自分自身に遡及してくるかを感ずるのである』と。このようにユーモアの立場は、アイロニーの立場をより徹底化した方向でより深くより高次な立場であることによって、アイロニーの立場を一回転深くのり超えた立場である」(大谷・前掲書292頁)。
次に、ユーモアの特徴とは何にか。これも少々長くなるが、大谷がキルケゴールの文章を引用して説明しているので、その部分を書き出すことにする。
「第一に、ユーモアは、共感性を本質としており、それは『共感的な笑いの立場』である。これはアイロニーの立場が優越性を本質としており、優越的な笑いの立場であるのに対して正反対である。キルケゴールは言う『アイロニーには共感というものが含まれていない。アイロニーは自己主張だからである。しかしユーモアには共感が含まれている』と。……
第二に、ユーモアには苦悩が隠されている。キルケゴールは言う『ユーモアの中にはつねに苦悩が隠されている。それだからこそユーモアの中にはまた共感というものがある。……ユーモアの人が語るときに涙と笑いが同時に誘われるのは、彼の内部につきささっている苦悩の痛みとしかもそれが転じられたものとしての冗談とのこの二つの故である。』『アイロニーは自己本位である。アイロニーは俗物性と闘うが、にも拘らずそれをもち続ける。……アイロニーは、自分自身を見つめているが故に、自分自身を打ち殺せないのである。しかしユーモアは抒情詩的である。それは最も深い生の真剣さである。しかし抒情詩という形をとることができないので、最も奇異な形式をとって現われる詩になる。それは流れ去ることのない黄金の鉱脈であり、より高い意味での苦悩発作である。』『アイロニーの人がユーモアの人の機知や着想を一笑に付して問題にしないとき、それは、ハゲタカがプロメテウスの心臓を喰ってゆく場合と同じようなものである。なぜなら、ユーモアの人の着想はきまぐれの落とし子ではなくて、苦悩から生まれた息子たちであり、彼の最も深いところにある心臓はその息子たちの小さい心臓と共に活動しており、しかもこのユーモアの人の深い絶望を必要とする者は、その痩せ細っているアイロニーの人だからである。……ユーモアの人の笑いとその眼差しは、そのような人間の惨めさに泣いていることを現しているのである。』『私は思うのだが、人は苦しめば苦しむほど、ますます滑稽さへのより豊かな感覚をもつものだ。もっとも深い苦悩を通じてはじめて人は滑稽さにおける真の権威というものを獲得するが、この権威は、人間と呼ばれている理性的生物を、魔法の一撃によって、漫画に変えてしまうのである。』
第三に、ユーモアは、アイロニーよりもはるかに深いスケプシス……に、いや、絶望と負い目の意識に基づいている。キルケゴールは言う『ユーモアは、アイロニーよりはるかに深いスケプシス……を内包している。なぜなら、ユーモアにおいては、一切のことが、有限性をめぐってではなく、罪性をめぐって動いているからである。』『アイロニーとユーモアとは自分自身を反省する。それ故に無限の諦念の領域を自分の住家とする。』『ユーモアの色合いとは、背後にひかえていた永遠なる決定性のもとで、全体的なものを無限に撤回してゆくことである。』『ユーモアとは、人と人との間に相対性を設定するとともに負い目を全体的に設定することによって、喜劇的なものを発見する。喜劇的なものは、全体的な意味での負い目というものが根底にあるということがらのうちにある。』『ユーモアは一切のものと一緒に負い目の意識の永遠性の想起を設定するが、自らは永遠の至福に関係しない。こうして今やわれわれは、ユーモアにおいて隠された内面性のそばに立つのである。』」(大谷・前掲書294頁)。
このようなユーモアの特徴から、以下のような「ユーモア」の構造が明確になる。
「このように考えてくるとき、ユーモアの構造がはっきりしてくる。即ち、ユーモアの立場は、自分を含めて現実の全体性を相対化する立場であり、その相対化によって相互の人間性肯定をよろこぶ立場である。しかしこのことをユーモアは徹底的に逆説的な仕方で遂行する。それはその運動が生き生きと働かなければならないためである。……アイロニーは相手や対象をいかにも肯定するふりをして、実はそれを徹底的に否定するが、これとは反対にユーモアは、相手や対象をいかにも否定するふりをして、実はそれを肯定しようとする立場である」(大谷・前掲書294頁)。
3.大谷によって、「価値の逆説」の問題はどのように処方されたのか、それについてこの章を閉じる前に観ておく必要がある。
「以上しばらくの間私(大谷)は、価値の問題は逆説との出会いを通じてという仕方ではじめて問題になりうるという前提のもとで、その逆説の問題として、アイロニーとユーモアの概念について述べてきた。この両者は、それぞれ実存の立場を表徴するものとして、現に生きられ志向されている『価値』の質を表徴するものである。そこでこのような観点から歴史上の各時代の質を考察するとき、それらはその正体を非常にはっきりと現してくるように思える。そして少なくともルネッサンス以降今日に至るまでの近世という時代は、その間に生まれた哲学、思想、そして生き方の殆んど悉くがアイロニーによって根本から規定されている時代であったことがつくづくわかるような気がする。そして今日はそれが極点に達した時代であることがわかる。そうしてそうであるが故にこそ今日は危機の時代なのである。従ってこの今日の危機を救おうとして、この近世生まれの、つまり根本的にアイロニーに規定された哲学、思想、生き方をどんなに駆使してみても、それは不可能であることは火を見るよりも明らかである。そこでこの今日『新しい価値の創造』という問題が考えられなければならないとするなら、それは、近世の今までの価値の根本規定がアイロニーであったことを知り、これからの価値の根本規定はユーモアでなければならないことを理解し、このユーモアを根本規定とした哲学、思想、生き方をつくりだすことでなければならない。しかしそれが真になされうるためには、ユーモアによるあの『相対化』に深い意味を見出し、それに対して畏敬の念がもたれなければならないが、そのことは本質的に宗教的な在り方を意味していることなのである。宗教的なものを根拠としてはじめてあの『相対化』は神聖な意味をもつであろう」(大谷・前掲書295-296頁)。
三.大谷愛人、あるいはキルケゴールの「新しい価値創造」の議論の問題点
全焼において、大谷によるキルケゴールの「新しい価値の創造」の説明を詳細に観たが、当然のことながらそこには論者のバイアスが入っていることに注意しなければならない。
1.まず、「新しい価値の創造という問題について」の「危機的状況」とは何時の状況なのかという疑問がわいてくる。大谷の説明を読むと、それは「新しい価値の創造」との関係で語られているので現代の状況の問題のように思える。なるほど、大谷は「現代」なる語ではなく、「近世」の語を用いているので、「現代」と「近世」は異なると言えなくないが、これは「モダン」の訳語の相違に過ぎないと解することも可能である。しかし、大谷がここでの説明で大きくキルケゴールに依拠している以上、「危機的状況」=「危機の時代」はキルケゴールの問題視した「市民社会の危機」を対象とした処方箋でなければならないだろう。ここでは、以下の藤野寛の引用が有効であると思われる。曰く、「これは皮肉な事態であった。人々が、危機などということはなんの縁もなさそうに自由と教養と進歩を享受・謳歌し、言うなれば温泉気分に浸って生きていた17世紀前半のコペンハーゲンで、人生がたえざる危機の連続であることを訴え、キリスト教界をその安逸から引きずり出そうと孤立無援の戦いを挑んだ……。それが、20世紀に入り、ヨーロッパの市民社会が、誰の目にも見まがいようのない仕方で危機的様相を呈し始める。キルケゴール自身は、キリスト教徒であることを困難ならしめることを意図して著作活動を進めたのだが、20世紀に入り、人々は人間として生きること自体に困難さを直視させられることになったのだ。そこに(50年の時差をもって)キルケゴールが発見されたのである。人生の否定性の思想家、不安・絶望・憂愁・孤独・水平化を仮借なく分析した思想家キルケゴールが」(藤野寛「キルケゴール」須藤責任編集『哲学の歴史<第9巻>反哲学と世紀末』(中央公論新社、2007年)261頁)。ここで、大谷の説明がこの時差と、ヨーロッパ社会と日本社会のキリスト教の受容の程度の差を読者に説得力を持って伝わるのかという疑問がぬぐいきれない。
2.次に、大谷の以下の説明は誤解を生まないであろうか。「……今までの価値の根本規定がアイロニーであったことを知り、これらの価値の根本規定はユーモアでなければならないことを理解し、このユーモアを根本規定とした哲学、思想、生き方を作り出さなければならない。」この文章を素直に読むならば、アイロニーとユーモアのパラダイム・シフトがなんの葛藤もなくおこなわれているように思われるが、それはキルケゴールの真意をつくものではないように思われる。これも藤野の以下の説明を借りれば分かりやすい。
「キルケゴールが障害どれほど熱烈にソクラテスを賛美し続けたかは尋常ならざるものがある。……プラトンにおいては『弁証法』は真理認識の方法に関る問題だった。キルケゴールに言わせれば、ソクラテスにおいてはすでに『みずからの無知を自覚し、かつそれに耐える』一つの生き方として実践されていた」(藤野・前掲書230-231頁)。「キリスト教徒であることは、イエス・キリストの生にまねぶこと以外ではありえない。『迫害され、忌み嫌われ、嘲笑され、嘲笑される』ことだ。『祝福され、称賛される』こと、『従順は守られる慣習だの、良き礼儀作法だの、それに類すること』は、キリスト教であることとは『絶対的に対立する』」(藤野・前掲書221頁)。すなわち、大谷の「新しい価値の創造」の説明はオブラートにつつまれていて、本来のキルケゴールの議論のもつ「反時代的」(藤野・前掲書227頁)、「アブラハムの苦悩」(藤野・前掲書249-250頁)といった峻厳さが見えにくくなるのではないか。
3.本レポートの8頁目に記したアイロニーの特徴のもつ問題点につてい、これは大谷が自ら自覚し、それについて言及しているのでここで概観することにする。内容は以下である。
「アイロニーは、自我がアイロニーの本質を、とりわけそれをうちに動めく 無限性を熟知して、そのアイロニーよりそれがより徹底化された意味でのより高次の立場から、自我によって支配、或は、統御されてている場合には、アイロニーは、自我が、それのそのような本質を全く知らないために、アイロニーを行使しようとして逆にアイロニーに隷属し、アイロニーに支配されてしまうという点である。つまり、アイロニーが否定しようとしているのは、現実全体がもとうとするその『絶対性』に対してであるが、自我はアイロニーによってその『絶対性』を無限に絶対的に否定してゆく間に、いつの間にかその『無限にして絶対的な否定性』の働きのうちに巻き込まれ、呑み込まれ、自らがその『無限にして絶対的な否定性』そのものと化してしまい、それをこそ否定対象としていた筈の当の『絶対性』へと化してしまう。しかもその『無限にして絶対的な否定性』そのものが実体化し固定化して『優越的笑いの立場』として機能するようになる。つまり、絶対的に優越的な立場から『無限にして絶対的な否定性』を働かせることになる。そうなれば、それは結局、絶対的な自己主張による絶対的な他者否定の立場以外の何物でもなくなる」(大谷・前掲書290-291頁)。もちろん、「絶対的な自己主張による絶対的な他者否定の立場」を明らかにして、ユーモアの必要を説く必要があることは理解できるが、この説明は論理的であるとは言え、冗長にすぎるように考える。この説明を簡略化して、「自我それ自身を笑える立場」に立つ必要性をどのように導出するのかは私自身に対する残された課題である。
-以上ー
<参考文献>
①大谷愛人・池上明哉・小松光彦『現代倫理学の諸問題』(慶應義塾大学出版会、2012年)
②須藤訓任責任編集『哲学の歴史<第9巻>反哲学と世紀末』(中央公論新社、2007年)
③大谷愛人『キルケゴール教会闘争の研究』(勁草書房、2007年)
④『キルケゴール著作集6』(白水社、1995年)
⑤『世界の名著51・キルケゴール』(中央公論社、1979年)
⑥『世界の大思想24・キルケゴール』(河出書房、1966年)
(コメント)2013..10.11.
テキストのキルケゴール理解を批判するものであれば別に二次文献ではなくキルケゴール本人の著作を引用すべきです。藤野氏の記述が妥当であるかどうかも、結局は一時文献を読まなければ分かりません。
参考文献④~⑥はキルケゴール自身の著作ですが、これを活用した成果を反映できればよいものになります。
(西山)
社会学史Ⅰ
一.まず、私自身は最初、デュルケムの『社会分業論』か、『社会学的方法の基準』でこのレポートを作成しようと思っていたが、地元の公共図書館や、神保町の古本屋街で入手することが出来なかったので、デュルケムの『自殺論』を選び、それに基づいて要約ないし、現代社会論を論述することとする。ただし、デュルケムの『自殺論』は自殺の動機という心理的な問題に関心を向けるというより、上述の2冊の延長線上にある自殺についての社会的要因に関心を向けているので、社会連帯と分業、あるいは社会的事実と集合意識に関心をもった私には興味深いものであった。そもそも、デュルケムの社会連帯と分業、あるいは社会的事実と集合意識に関心を持ったのはTPP亡国論の主要論者である中野剛志が、しばしばその著作の中でデュルケムの著作を引用していたからである。
二.まず、彼の自殺論は「第一編 非社会的要因」、「第二編 社会的原因と社会的タイプ」および「第三編 社会現象一般としての自殺について」に分かれる。しかしながら、自殺についての社会的要因に比重を置くデュルケムであるならば、その論述の重要性は第二編以降の記述に置かれるであろう。たとえば、デュルケムはプロテスタントとカトリックの集団のあいだの自殺率の相違に着目して議論を展開することはよく知られているところである。もちろん、彼は第一編・第一章二以下において、プロテスタントとカトリックの集団のみならず、ユダヤ教徒の集団まで加えた上で自殺率の相違を論じている。しかし、そこに書かれているのは以下のようなものである。「精神病は、他のどの宗教よりもユダヤ教徒にはるかに多発していることがわかる。それゆえ、神経系統の他の疾患についても同様だと考えるのは大いに根拠があろう。ところが、自殺傾向のほうは、正反対に、ユダヤ教徒のばあいきわめて小さい。のちに(第二編・第二章)に筆者(デュルケム)は、これが自殺傾向のもっとも弱い宗教であることをしめすつもりである」(デュルケーム・宮島喬訳『自殺論』(中央公論新社、1985年)57-58頁)と。そして、デュルケムは『自殺論』第二編・第二章 自己本位的自殺にその分析をゆずるのである(宮島訳・前掲書171頁以下)。すなわち、彼は自殺を「社会的原因と社会的タイプ」という社会学的説明をもって分析するのである。
そして、ここで彼はなぜ、カトリック信者(カトリシズム)に対してプロテスタント信者(プロテスタンティズム)の方が自殺率が高いのかという説明が開陳されるのである。
「宗教社会では、人びとは同一の教義体系むすびつくことによってはじめて社会化されるのであり、この教義体系がより広汎でしかも強固であればあるほど、人びとはよりよく社会化される。宗教的性格をおびた、それだけにまた自由検討に反するような行動様式や思考様式が数多く存在すればするほど、いっそう神の観念は生活のすみずみまで行きわたり、それによって、個々人の意思もただ一つの同じ目的に集中するようになる。反対に、宗教団体が個人の判断にすべてをゆだねていればいるほど、それだけ個人の生活からそのかげがうすれ、集団としての凝集性も活気も失われてくる。そこで、次のような結論に達する。すなわち、プロテスタンティズムのほうに自殺の多い理由は、プロテスタントの教会がカトリック教会ほど強力に統合されていないためである、と」(宮島訳・前掲書182頁)。桜井洋によれば、このことは「集合的な意識が希薄となれば社会は凝集力を失い、その結果道徳力も失われ、個人の生活は脆弱なものとなるほかはな」く、「集合意識の差異によって自殺率の差異」を説明するものとされる(那須壽編『クロニクル社会学』(有斐閣アルマ、1997年)31頁)。
このような社会の、あるいは集団の「凝集性」の差異に基づいてデュルケムは自殺の3類型論を展開する。第1は「自己本位的自殺」であり、第2は「集団本位的自殺」であり、そして最後に第3は「アノミー的自殺」である。以下、この類型についての説明は章を変えて行うこととする。
三.まず、第1の「自己本位的自殺」とはなにか。デュルケムによれば、以下のように説明されることになる。
「よく、人間は二重の存在であるといわれる。それは、物理的人間の上に、社会的人間が重ねられているからである。ところで、社会的人間はかならず社会の存在を前提とする。かれが表現し、役だとうとする社会を。ところが、社会の統合が弱まり、われわれの周囲やわれわれの上に、もはや生き生きとした活動的な社会の姿を感ずることができなくなると、われわれの内部にひそむ社会的なものも、客観的根拠をすっかり失ってしまう。それは、もはや空虚な心象の人為的な結合物、あるいはいささかの反省によっても容易に霧散してしまうような一個の幻影にすぎなくなる。すなわち、われわれの行為の目的となりうるようなものは消滅してしまうのである。ところが、この社会的人間とは、じつは文明人にほかならない。社会的人間であることが、まさにかれらの生を価値あるものにしていたのである。このことからして当然、〔社会の統合が弱まると〕かれらの生きる理由も失われることになる」(宮島訳・前掲書254頁)。
次に、第2の「集団本位的自殺」とはなにか。デュルケムによれば、以下のように説明されることになる。
「(集団本位的)自殺が行われるのは、当人がみずから自殺する権利をもっているからではなく、それどころか、自殺する義務が課せられているからである。かりにこの義務を怠ると、恥辱をもって罰せられるか、あるいはより一般的なケースとしては宗教的な懲罰をもって罰せられる」(宮島訳・前掲書262-263頁)。ここで、未開社会における自殺が説明される。
最後に、第3の「アノミー的自殺」とはなにか。デュルケムによれば、以下のように説明されることになる。
「しかし、このことは、危機が勢力と富の突然の増大に由来しているときでも、いっこうに変わらない。じっさい、その場合も、生活の諸条件は変わってしまうので、それまでの欲求を規制してきた尺度は、各種の生産者に帰せられるべき配分をほぼ規定しているので、社会的な諸手段のあり方が変われば、尺度も変わるからである。こうして段階規定は混乱してしまうが、さりとて、新しいそれが、時をうつさず用意されるわけにもいくまい。人と物が世人の意識によって新たに分類されるまでには、時間を要する。こうして、いったん弛緩してしまった社会的な力が、もう一度均衡をとりもどさないかぎり、それらの欲求の相互的な価値関係は、未決定のままにおかれることになって、けっきょく、一時すべての規制が欠如するという状態が生まれる。人は、もはや、なにが可能であって、なにが可能でないか、なにが正しくて、なにが正しくないか、なにが正当な要求や希望で、なにが過大な要求や希望であるかをわきまえない。だから、いきおい、人はなににたいしても、見境なく欲望を向けるようになる。この動揺がすこしでも深刻になると、それは、各職務への市民の配置を規定している当の原理にまでおよんでいく。なぜなら、社会のそれぞれの部分の関係が、そのまま存続するわけにはいかなくなるためである。危機のおかげで特別の利益にあずかった階級は、もはやそれまでのような忍従に甘んじていることはできない。また、そのことへの反動として、その階級のより大きな富をまのあたりにした周囲の者、あるいは下位の階級の者は、ありとあらゆる羨望をそそられる。このように、欲望は、方向を見失った世論によってはもはや規制されないので、とどまるべき限界がどこにあるかを知らない。そのうえ、このときには、一般に活動力が非常に高まっているため、それだけでも、欲望はひとりでに興奮状態におかれている。繁栄が増すので、欲望も高揚するというわけである。欲望にたいして供されるますます豊富な餌は、さらに欲望をそそりたて、要求がましくさせ、あらゆる規制を耐えがたいものとしてしまうのであるが、まさにこのとき、伝統的な諸規制はその権威を喪失する。したがって、この無規制あるいはアノミーの状態は、情念にたいしてより強い規律が必要であるにもかかわらず、それが弱まっていることによって、ますます度を強める」(宮島訳・前掲書310-311頁)。
四.以上の『自殺論』の社会学における意義とはなにか。桜井によれば、次のように評価されることになる。
「『自殺論』は、通常はもっぱら心理学的に理解される自殺という概念を社会学的に分析したという点で、社会学的分析の意義を明示した記念碑的な著作である。自殺という課題を考えることは、個人と社会という社会学の根本問題に正面から取り組むことを意味する。デュルケムは統計データを多用することで自殺という問題を、その動機という心理学的コンテクストから社会学的なコンテクストに置き換えたのである。彼の用いた統計的手法それ自体は当時の水準からしても格別に画期的なものであったわけではない。『自殺論』の意義は、統計データを用いることによって、相互行為のシステムにおける社会システムの領域を分析的に抽出した点であるのである」(那須・前掲書32-33頁)。
五.この書物の視点から現代社会を論じるとするならば、2012年度は3万人を割ったが、それまで15年間3万人以上の数で推移してきたわが国の自殺者数をテーマに論述していくのが良いと思われる。デュルケムは上述のように、自殺の3類型を説いたが、日本においても会社組織等に殉死するかのような労働観が残っていることはまず措いて、個人主義が根づいてきたとするならば第2の「集団本位的自殺」よりも、第1の「自己本位的自殺」および第3の「アノミー的自殺」を中心において論じる必要があろう。しかしさらに、日本においては、デュルケムが「自己本位的自殺」の考察の対象とした一神教的社会における社会的な凝集力の喪失はそのまま妥当しえないように考えられる。おそらく、日本人が宗教上の理由や倫理上の理由から自殺を選択することはほとんど無いのではなかろうか。(もちろん、「自己本位的自殺」は他の自殺類型と密接な関係に立つことが多いので、それを論じないで良いというわけではない。)とするならば、デュルケムの視点から現代社会現象たる自殺を論じる時に、中心となるのは「アノミー的自殺」ということになろう。桜井も指摘するように、デュルケムがアノミーの概念を提起したのは19世紀末の近代資本主義の爛熟期であり、以前の宗教や職業組織などの規範力は力を失い、人々は自己の欲望のコントロールを失ってしまった。しかし、産業社会以後の現在では、およそ1世紀前のデュルケムの時代をはるかに越えた社会的価値の変動が生じている。それは、現代社会に生きている人々が、彼の時代を上回るアノミーに直面しているということである。国民国家や近代家族といった、近代の価値を支えてきたシステムも大幅に揺らぎはじめている。であれば、肥大化する欲望が跋扈する現代社会はアノミーが社会の「正常な」状態になってしまい、それに基づいて「アノミー的自殺」も常態となってしまうのではないか。又、2012年度、自殺者数が減少したのはどうしてなのかという更なる問題が生じてくる。それは、社会学の残された問題なのではないだろうか?
―以上―
<参考文献>
①那須壽編『クロニクル社会学―人と理論の魅力を語る―』(有斐閣アルマ、1997年)
②デュルケーム・宮島喬訳『自殺論』(中央公論新社、1985年)
(コメント)2013.11.13
デュルケムを用いて現代日本の自殺についてていねいに考察がなされています。
(濱)
午後6時過ぎに、ファミレスで久しぶりに豪華な食事をする。

この日のニュースは、やはり宮崎駿監督の長編アニメーション製作からの引退だろう。特に、このニュースの第一報がNHKであったことにはビックリした。
しかし、ハッキリ言って「となりのトトロ」以降のアニメって宮崎監督の自己満足映画であり、晩年の醜態を晒さずに済んだいい引き際だとわたしは思う。これとの対比で、「どですかでん」以降の黒澤明監督のカラー映画が駄作の連続だったので、「まあだだよ」を出したときに「もういいよ」と思ったのはわたしだけではあるまい。映画評論家の品田某氏が引退を惜しんでいたが、ほんとか思った。事実、国内のみならず海外のネットまで「やめるやめる詐欺」であると書かれているのだから、観る人がみればよい花道だったと思われる。もちろん、わたしは「ルパン三世 カリオストロの城」、「風の谷のナウシカ」および「天空の城ラピュタ」は名作であると思っているので、宮崎作品の全部を駄作だと思っているわけではないことを付け加えておく。