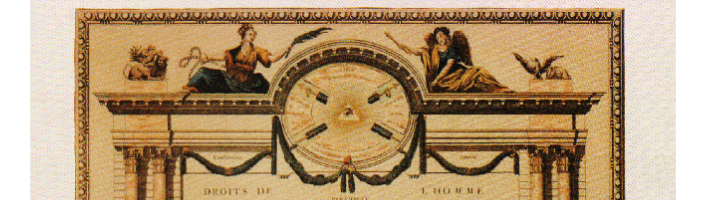倫理学
12月5日の備忘録。
8時23分に、近くのマクドナルドで以下のものを買ってくる。
チキンエッグマフィンセット 530円
チキンエッグマフイン
ハッシュポテト
アイスカフェラテM
県立図書館に行って、倫理学のレポートをまとめる。
第1章 はじめに
ユダヤ・キリスト教の倫理思想を、通教テキストを通読した上で、関根清三『ギリシア・ヘブライの倫理思想』(東京大学出版会、2011年)の第9章「ヘブライの宗教倫理と贖罪思想―『イザヤ書』『第二イザヤ書』を中心に」に則して説明していくことにする。なぜならば、この章こそが、ヘブライズムの倫理が贖罪信仰たるキリスト教へと「究極」することを説明しているからである(関根・前掲書299頁)。
第2章 『イザヤ書』のアンビバレンツ
イザヤは預言者として神から召命を受けた時、「民が「立ち帰って癒されることのないため」に預言せよ」、という使命を与えられた。しかしふつうは、預言というものは、「民の立ち帰りと癒しを目指すように思われる」ものである(前掲書273頁)。関根は、これを《イザヤは主観的には民の悔い改めと神からの救済を意図して預言したけれど、その預言が客観的には結局、民の頑迷と神からの審判を結果した》と解する。しかし、このように解したとしても、どうして預言の主観的意図と客観的結果の間に、食い違いが生じたのかの説明が必要となる(前掲書274頁)。関根は、C・G・ユングや湯浅康雄の議論を用いて以下のように説明する。
「預言者は民の道徳的不正に終始固執したけれども、民の罪は、あるいは総じて多くの犯罪というものは、無意識領域からの救済の力を制御し得ない、意識の無力から起こっているのである。だが預言者のように意識の道徳的判断のみを頼りにしてそういう衝動を禁圧しようとすれば、むしろ自然悪の力を増大させ、その抑圧され溜まりに溜まった悪の力の爆発という形でより多くの道徳的悪を生み出す場合が少なくない。道徳的訓戒は、悪の大きな力にとらえられた人間に対しては無力である。《これは罪だ、そのことを認めよ》といった論理によって、悪の力が消滅するというものではない。悪はむしろ、そういった裁きではなく、むしろ忍耐強い愛の力によってこれを馴化し、矯正して行くほかはない」(前掲書275頁)。
こうした預言者の義の神においては、他者関係の罪は自覚されることなく、したがってその関係の修復もあり得ないとするならば、では愛の神はどうかという次の問いが生じてくることになる。
第3章 ダビデにおける「罪の赦し」
ここで次に議論されなくてはならないのは、ダビデのバテシェバ事件を主題とした『サムエル記下』11-12章および『詩篇』51篇の解釈である。関根は、P・リクールを用いて以下のように説明する。
「すなわち、罪の赦しが告知されて初めて告白もなされるというのが、その答えに外ならない。ナタンがダビデを当てこすった寓話を話しても、ダビデは自分と関係のない話だと思っていた。それほど罪は理性の認め難いものであり、自他に対して隠蔽しがちなものである。しかしナタンを通して神からの罪の赦しが告げられた時、ダビデは赦された当のものが、実は罪であったことに気づき、それを認め告白する勇気を与えられた。こうして「私の罪は、常に私の前にある」という認識が初めて彼のものになったのである。罪はそれ自体としてはなかなか認め難いものであり、ただ弾劾されても人は無数の言い訳をするだけだろう。イザヤの頑迷預言で見た通り、それが弱い普通の人間の性なのであろう。だが弾劾ではなく赦免が語られる時、人は罪がそれだけで単独の概念なのではなく、赦しとの相関概念であったことを知るのである。すなわち、それまで漠然と悪いことをしたと思っていても、罪と呼ぶほど大層なものではないと高をくくっていた、過去の行為が、赦されて初めて、完膚なく語の十全の意味で罪そのものであったと気づくものだということ」(前掲書278-279頁)。
このことを前提に、『詩篇』51篇「あなたに、ただあなたに罪を犯した(レヒャー・レバデヒャー・ハーターシー)」の解釈を以下のように解すべきであると関根はいう。
「つまりレバデヒャーは、「とりわけあなたに」とでも訳した方が、原意に沿っているのである。そうしてこう訳すならば、「ただあなた(神)に」と訳していたときのアポリアが解けるのである。これは、対人関係の罪を免罪されるための遁辞ではない。むしろ「とりわけあなたに、私は罪を犯し」という言い方は、ダビデの罪の当体である殺人の相手ウリヤへの思いが言外に込められているのである。「とりわけ」というのは、他に比べて殊に、の謂であって、神以外のその「他」とはウリヤを指すほかはないからである。つまり「ウリヤに私は罪を犯しました、そしてあなたが忠実な武将として私に与えてくださったウリヤに罪を犯したことによって、私はとりわけあなたにも罪を犯したのです」という告白が、この一句の意味ということになるだろう」(前掲書281頁)。
このようにして、次の第三番目のポイントが明らかにされた。つまり、関根によれば以下のように説明される。
「ダビデはそれまではどうにかして神と出会おうとして来た。例えば敬虔な祭儀行為や見栄えのよい事業によって神の歓心を買おうとした。しかし無駄だった。王としての説教や、人前で堂々と語れるような思想を通してもゆはり神とは出会えなかった。しかしそうではなくて、自分の中のひそやかで邪まな欲望、惨めな自己正当化の願い、人前で語れないような恥、そして何よりもそれらに働き動かされて取り返しのつかないことをした負い目と悔恨、そういった自分に染み付いている「罪」としか名付けようのない、心の「秘められた所」、そこで辛うじて神に出会ったというのが、ダビデのここでの発見なのである。それは、あの預言者イザヤのような義の神ではなく、愛の神、赦しの神との出会いであったと言ってもよいであろう」(前掲書282頁)。
しかし、以下のような疑問が倫理思想の観点から残されることになる。
「すなわち、愛する妻を王に寝取られ、その地位を利用した王の画策によって殺されてしまったウリヤの無念はどうなるのか、その被った悪はどう償われるのか、このダビデの歌はあまりに虫のよい加害者の、神を笠に着た予断に基づくのではないか、彼は自らの犯した罪の責任をどう取るのか、そもそもこのように罪悪を罰せずに闇雲に罪悪を赦す神の正義は如何にして弁証されるのか」等々である(前掲書283頁)。
第4章 『第二イザヤ書』の贖罪思想
これまでの説明をした上で、関根は「義か愛かどちらかに偏るのではなく、両者を統合するような神を我々は更に捜し求めなければならない」とする(前掲書283頁)。そうした神の発見を、彼は『第二イザヤ書』のいわゆる「第四の僕の詩」に見出すのである。
「ここで「彼」すなわち、神の僕、が誰かについては数多の説がある。その詳細について、ここでは立ち入らないが、結論として私は、個人としては、将来現れるべきメシアと第二イザヤ自身を指し、集団としてはイスラエル全体を含意すると考える。そうした複数の読み込みを許す象徴的な書き方がなされていると解するのである。……いずれにせよ、ヘブライ人の「驚き」の対象は、突き詰めたところ神の業であったが、この神の僕において、神の業は究極的な姿で「現れた」と言われる。その業こそ、周囲の「多くの国民たち」から、僕の身近にいた「我ら」に至る、総ての人を驚愕させたというのである。ではその「驚」くべき業の具体的内容とは何か。それは次の数節(同書53章4-5節)に集約される。
…… ここに、旧約聖書中唯一無比の贖罪思想が語られている。すなわち、「苦難の僕」と呼ばれる義人である「彼」への苦難は、理不尽に下されるのではなく、贖罪的意図のもとに下されていたというのである」(前掲書285頁)。
これが、新約においてどのように「究極」するのか。これについて、関根は以下のように説明する。
「なお動物犠牲に始まり、執り成しの祈りといつ人間の犠牲の可能性、そしてこのイザヤ書53章の人間犠牲の現実態を経て、新約聖書(キリスト教)では、動物でもなく人間でもなく神自身が己の独り児を犠牲として捧げる究極的な形になると考えられていることを、ここでは一言付言しておきたい。……
主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられた。(『ロマ書』4章25節)
神はキリスト・イエスを、その血による、また信仰による、なだめの供え物として、公にお示しになった。それはご自身の義を現すためだ。というのは、今まで犯されて来た罪を、神の忍耐をもって見逃して来られたからだ。(同書3章25節)
私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられる。(同書5章8節)
あるいは、
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物として御子を遣わされた。ここに愛があるのだ。(『ヨハネの第一の手紙』4章10節等々……)」(前掲書287-288頁)。
このように、『第二イザヤ書』を結節点としてユダヤ教の「義」とキリスト教の「愛」とが統合されたのである。関根はそのことについて以下のようにいう。
「ここでは、ヘブライの人々が真の対象とした、倫理的行為に報いる応報の神など本当に存在するのか、という、前章からのあのヘブライ思想の根幹を揺さぶる問いに対する一つの究極的な解答が示されていると言ってよいであろう。罪人が栄え、義人が苦しむ現実は、旧来の応報思想では説明できなかった。こうした現実を応報ドグマによっていたずらに糊塗するのでもなく、と言って、コヘーレスのように応報思想を全く否定し、他者関係における不義の現実は嘲笑するだけでエゴイスティックな個人の快楽に神を見出すのでもなく、あるいはイザヤのように、義による裁きの神を告げるだけでも、ダビデのように愛による赦しの神にすがるだけでもなく、応報の原理が機能しないこの世の現実をありのままに視野におさめつつ、それを言わば逆手に取って、正にそこでこそ現れる神の発見がここで語られているのである。すなわち、ただ愛をもって闇雲に赦すだけならば、神の義は弁証されないが、一人の人に多くの人の罪を代わって贖わせ、そのことによって義を貫徹し、しかも多くの人に対する赦しの愛を成就する神の発見である。我々の経験する現実と齟齬しない真に驚くに足る神は存在するのか、という、あのヘブライの倫理思想の究極の問いに対して、旧約から新約に至る系譜が幾多の紆余曲折を経て辿り着いた、結論がここにはある。すなわち、直接的な倫理的応報の神は存在しないが、代理贖罪という間接的な形で応報を貫徹する神が存在する、というのが、その結論の内容にほかならないのである」(前掲書288-289頁)。
第5章 むすびにかえて
最後に、関根のまとめをもって本稿をしめくくることにする。
「「驚き」を標榜するヘブライの倫理思想の根幹を揺るがす問題を私は、倫理的行為に報いる応報倫理的な神が果たして存在するのか、という問いに見出した。この問いは、コーヘレスのニヒリズムによって否定的に答えられたが、コーヘレスがこれに代えて持ち出して来た神は、他者連関を無視したエゴイスティックな快楽において感じ取られるというだけの代物だった。そこで我々は続いて『旧新約聖書』の他のテクストに、直接的な応報という「統一的秩序」が破綻しているというニヒリズムの冷徹な現実認識は踏まえつつも、しかし他者関連という人間の根本的な存在様式も視野に入れた新しい神観を模索せねばならなかったのである。イザヤやダビデ等の紆余曲折を経て、第二イザヤの53章、そしてパウロを始めとする新約の諸書に至ってようやく、他者連関における応報の破れを前提としつつ、その破れにこそ他者の罪を負った贖罪的意味を見出す神が発見されたのである。パウロの引用にあったように、そこでこそ「ご自身の義を現」わし、同時に「愛を明らかに」する神と、人は出会ったのである」(前掲書294頁)。
-以上-
<参考文献>
①関根清三『ギリシア・ヘブライの倫理思想』(東京大学出版会、2011年)
②関根清三『旧約における超越と象徴―解釈学的経験の系譜』(東京大学出版会、1994年)
③関根清三『旧約聖書と哲学―現代の問いのなかの一神教』(岩波書店、2008年)
④福岡安都子『国家・教会・自由―スピノザとホッブズの旧約テクスト解釈を巡る対抗』(東京大学出版会、)
(追記:2014年2月3日補足)
講評:A合格(佐藤先生)←よかった
テーマ設定に即した展開があり、注意深い読解に値するレポートであると思います。