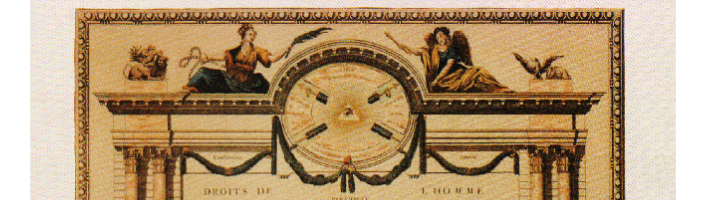国法学講義ノート 憲法秩序
第20章 憲法秩序
茨城大学准教授 中野雅紀
第1節 国法秩序の構造
(1)総説
国法体系においては、憲法を頂点とするヒエラルヒーが存在する。そして、このヒエラルヒーは偽ディオニュシオス・アレオパギデスの「天上位階論」と「教会位階論」に基づいている。そもそも、この位階の語源はhierarchiaで天使、および教会内の聖職者の階級を秩序付けるものであり、世俗の秩序とは無関係に語られていたのであるが、これが世俗化された近代国家の社会システムの説明に転用された。天使の位階は上位位階、中位位階および下位位階の三位階に分かれ、それぞれ上位天使には熾天使、智天使、座天使、中位天使には主天使、力天使、能天使および下位天使には権天使、大天使、天使に分かれる。ここで重要なのはこの思想が「超越的一者たる神が充溢する善性による被造物に発出して下降する秩序であり、一から多への展開過程である」とすることである。すなわち、ケルゼンのような法段階説を採った場合、法秩序の頂点には唯一の根本規範が存在し、それが下位の法規範を基礎付ける。反対に、ある法規範の根拠を問えば、それを根拠付けるより上位の法規範が存在し、それが最終的には一つに収斂する。これに対して、そのようなものは存在しないとすると、それに根拠付けられたピラミッド体系をした法秩序という釣鐘は支点を失い地上に落下してしまう。日本国の国法秩序もさまざまな法規範から構成され、これらの法規範は一つの纏まったヒエラルキーをもつ構造を形成している。最高規範が憲法であり、その下にピラミッド状に法律、命令、規則、条例などの国内法の諸形式が序列化され(98条1項)、「憲法の最高法規性」と「憲法の授権規範性」を基礎付けている。
以上のように、国法秩序は憲法を頂点として構成されている。であれば、旧憲法とはまったく異なった原理に基づく新憲法が制定された場合、旧憲法に下に成り立っていた国法秩序は理論上、すべて無効となる「べき」であろうか。これ関して、最高裁は憲法98条の「反面解釈として、憲法施行前に制定された法令は、その内容が憲法の条規に反しないかぎり効力を有する」と判断している(最大判昭24.4.6、明治憲法制定以前の法令の効力については最大判昭36.7.24)。また、占領中という「例外状態」における広範な「授権法」であり、連合軍最高司令官の要求を実施するために日本政府に認められた命令制定権に基づく、いわゆるポツダム勅令―これらは公職追放例令や物価統制法令の基礎となった―は、憲法外において効力を有していたが、このうち占領状態の継続を前提としている規定は昭和27 年の平和条約の発効後には効力を失い(最大判昭28.7.22)、そうでない規定は内容が憲法に違反していない場合、その効力は有効であるとされた(最大判昭36.12.20)。
(2)国法の諸法源
- 法源
国法秩序を構成する諸法の存在形式のことを纏めて「法源」といい、憲法、法律、命令、議院規則、最高裁判所規則、条例および条約などの「成文法」と慣習法、判例法および条理などの「不文法」に区別される。
2)成文法
憲法98条1項によれば、成文法の形式的効力について憲法が法律、命令、規則および条例に優先するが、同条2項には条約について国内法規範と条約の関係が規定されていない。
- 憲法
憲法の制定権者は国民である。現在、国民が実際に憲法を制定するのは改正による。憲法とは、国家の構造と作用を規定する基本法であり、国法体系中、形式上「最高規範性」を持つ。
- 法律
「二重法律概念」で示されるように、法律には議会手続を経て成立する法規範を「法律」という「形式的意味の法律」と、その一般的・抽象的規範性の本質をさす「実質的意味の法律」の二つ意味がある。法律で規定できる事項を法律事項といい、更に必ず法律で規定しなければならない必要的法律事項と、他の法形式によることも許されている任意的法律事項に分けられる。
まず、法律によることを憲法が明文で規定している事項が必要的法律事項である。例えば、憲法26条、29条、31条、44条、66条、76条、84条(該当条文参照)などがそれである。また、憲法41条の趣旨から、一般的・抽象的な法規範、つまり実質的意味の法律、そしてその立法はこの法形式によって定められなければならない。これは、国民の「権利を制限し義務を課す規範」の場合に重要である。実質的意味の法律に関する事項を法律以外の法形式で定める場合には、法律の委任がなければならない。最高裁は、例えば「罰則を設けることは、特にその法律に具体的な委任がある場合を除き、……法律を以って規定すべき事項」である(最大判昭27.12.24)とする。もっとも、実質的意味の法律で憲法自らによって58条・77条などは、特に法律以外の形式で制定することが許されている。任意的法律事項は他の法形式で規定することもできが、一旦法律で規定されると必要的法律事項となり、変更には法律の形式によらなければならない。
c. 命令
例外的に、行政機関が立法作用を認められ、これによる法形式を命令(狭義)という。
d. 議院規則
議院規則とは国会の両議院が、各々その議会その他の手続および内部の規律に関して定める法形式である。
- 最高裁判所規則
最高裁判所規則とは、最高裁が制定する法形式である。
- 条例
条例とは、地方公共団体が自治権に基づいて法律の範囲内で制定する、自治法の形式である。
- 条約
条約とは、国家あるいは一定の国際法主体を当事者として、その当事者間の書面の形式による合意であり、名称に限られず国家間の合意であれば協定・宣言・憲章などと呼ばれるものもそれに含まれる。
憲法98条2項の趣旨などを根拠として条約の形式的効力が法律に優位することは学説上争いがないが、憲法と条約の関係においては、条約が憲法に優位するとする条約優位説、憲法が条約に優位するとする憲法優位説、その折衷説として、憲法の基本原理は条約に優位するが、それ以外の憲法規定(憲法律)は条約の下位にあるとする同位説、さらに、例えば「世界人類が等しく遵守すべき普遍的原理」を内容とする法規などは、憲法がその基本原理を前提としているから、一定の条件付での憲法の優位を認める条件付き憲法優位説に大別される。ただし、同位説と条件付き憲法優位説には根本的な相違はない。
条約優位説の根拠は①日本国憲法は前文で国際協調主義、および9条で平和主義を謳っている、②法令審査権に関する81条に条約が挙げられていない、③98条2項の誠実遵守が憲法制定権を含むすべての国家権力を拘束する趣旨であると解せられことなどである。
次に、憲法優位説の根拠は①条約の締結権は憲法に根拠を有し、締結および国会による承認は憲法の枠内においてのみ許容される、②98条2項の誠実遵守は憲法と条約の関係について、有効に成立した条約の国内法的効力を認め、その遵守を義務付けるにとどまる、③司法審査権に関する81条に条約が挙げられていないのは、条約が国家間の合意に基づくものであるために裁判所の判断に適さないことに配慮したと考えられる、④日本国憲法は憲法改正については厳重な手続を定めているにも拘らず、条約優位説を採ればその手続によらないで憲法改正が簡単になされてしまうことなどである。
第三に、同位説の根拠は①憲法は基本的な部分と、それ以外の部分に分けられる、②序列構造をなしている憲法と条約を単純に同じレベルで論じるのは適当ではない、③国際協調主義を強調しても、国家の独立を前提とする限りその国の憲法の基本的部分は条約に優位すると考えるべきであることなどである。
学説では憲法優位説が多数説であるが、実務では同位説も戦前から引き続いて有力である。砂川事件(最大判昭34.12.16〔4〕)で、最高裁は統治行為論によって判断を回避したが、条約が「一見きわめて明白に違憲無効であると認められない限りは」司法審査権が及ばないと判示しているので、一般には憲法優位説を前提としていると解されている(「条約法に関するウィーン条約」46条)。憲法優位説を採っても、国際法が当然に司法審査の対象となり、現実に無効とされうるかは別の問題である。
98条2項は、条約と以外に「確立された国際法規」の遵守を規定している。この国際法規とは、ドイツ基本法25条の「国際法の一般的諸原則」のように、広く国際社会で拘束力のあると認められている国際規範をさすとされ、成文であっても不文であっても構わない。もっとも、何をもってこの「確立された国際法規」とするのかは問題である。
- 不文法
慣習法とは、制定行為を経ずに社会の中で慣行的に行われている法である。慣習法の成立の二要件は①継続的反復、②法的確信の形成であり、原則として慣習法の効力は成文法を補完するものにとどまる(法例2条)。
判例法とは、判例として存在する法をいう。この判例とは、先例拘束性をもって判決を導くために意味のある理由、つまり判決中の法律などの合憲・違憲の結論それ自体でなく、その結論に至るうえで直接必要とされる憲法規範的理由付けであるratio decidendiの部分である。わが国では一般に成文法主義を採り、判例は一定の場合を除いて、事実上の拘束力しか持たないと解されてきたが、実務上、最高裁は自らの憲法判例に、また下級審は最高裁の憲法判例に拘束されている。
条理とは、社会の一般的良識である。立法者が完全な予測に基づいて立法することは不可能であり、成文法には隙間できることは不可避である。これを補完するものとしてまず慣習法や判例法が、それでもなおこの隙間を十分に埋められない場合、その判断の基準として条理が必要とされる(明治8年太政官布告103号3条、スイス民法1条参照)。
第2節 憲法秩序の変動
(1)憲法保障
憲法は国家の最高法規であるが、政治社会は生き物と同様に不断の変化を免れえず、これに応じて憲法も生きた有機的組織として、その規範性を確保するための方法を講じる必要がある。このような状況に対してあらかじめ「憲法保障制度」を設ける必要がある。
憲法保障は「通常状態」と「例外状態」の二つに沿って、①通常の憲法生活において憲法を保障する平常的憲法保障と、②戦争、内乱、大規模な自然災害などのような例外状況において憲法を保障する非常的憲法保障に分かれる。①に属する日本国憲法の定める制度としては以下のものが挙げられる。すなわち、憲法に対する侵害行為を事前に防ぐ予防的機能を果たすもの、例えば憲法の最高規範性の宣言(98条)、憲法改正の厳格な手続(96条)、公務員の憲法尊重擁護義務(99条)、権力分立制である。また、憲法に対する侵害が起こってしまった後、それを修正する事後的匡正的機能を果たすものとして違憲法令審査権がある。②に属する保障としては、国家緊急権と抵抗権が挙げられる。日本国憲法が規定する制度では、参議院の緊急集会(54条)がこの国家緊急権に該当する。なお、法律レベルでも内乱罪(刑77条)、破壊活動防止法および無差別大量殺人団体規制法などがある。
(2)憲法改正
1)意味
まず、憲法は国家の基本法であり、容易に変更されるべきではない。しかし、社会および憲法もまた生きた有機的組織としてその不断に変化し、その変化に対応しなければならない。このようなに憲法の安定性と憲法の発展の要請を調整するために憲法改正が認められているが、それについては厳格に定められた方法が採られている。一般に近代立憲主義憲法においては、憲法の改正に慎重を期すため議会の議決の特別多数を要求するなど手続に加重された要件を定めるが、改正によっても変更できない基本原理(価値)を定めることが多い。厳格な憲法改正は、予防的憲法保障として重要な意義を持つ。
なお、憲法の変動で改正と区別されるべきものとしては憲法の「廃棄」と「廃止」がある。憲法の廃棄とは、革命によって旧憲法を排除する行為であり、憲法制定権力の変動を伴う。憲法の廃止とは、クーデターなどにより旧憲法を排除する行為であり、憲法制定権力は変動しないが基本理念が変更される。また、憲法の特定の条項についてだけ一時的に効力を失わせる憲法の「停止」や、特定の場合に憲法の条項を例外的に侵害する憲法の「破棄」も改正と区別され、さらに憲法の変遷もこの改正と区別されなければならない。
2)手続
日本国憲法は、その改正について厳格な以下のような三段階の手続を規定している(96条)。
国会の発議は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成によって行われる。この発議をするには国会で審議されることを前提としている。日本国憲法には、審議のもとになる憲法改正の発議権や審議の方法、あるいは国民に対する提案について明記するところがなかったが、平成19年に「日本国憲法の改正手続に関する法律」が制定されることで立法上の指針が示されることとなった。同法の制定に関連して改正された国会法68条の2によれば、憲法改正原案を発議するためには衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するものとされ、また同法102条の7によれば憲法審議会も改正原案を作成し、提出できるものとされ、いずれの場合にも「内容において関連する事項ごとに区分して行うもの」とされた。これを受けて、各議員の総議員の3分の2以上の賛成の決議があって、国会の発議・提案が成立することとなった。
憲法改正は、国会の決議を経た憲法改正案が国民によって承認されてはじめて成立するもので、その意味で国民主権の純粋な発現形態であり、ここに特に「特別な国民投票」とあるのはことの重大さに照らしてのことである。この「国民」の範囲はより多くの国民が投票に参加できる趣旨から、「日本国民で年齢満十八年以上の者」とされている(同法3条)。次に、承認の要件に関しての「過半数」については有効投票数の過半数説が採用されることで決着した(同法123条)。
国民によって承認された憲法改正は、天皇が「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして公布する」(96条2項)。
3)限界
上述のように、日本国憲法では限界についての明文規定が置かれておらず理論上、このような限界が認められるか否かが問題となる。
憲法の価値序列や憲法制定権力を否定して、改正手続に則っていればどんな憲法改正も可能であるとする法実証主義的学説や、憲法制定権と憲法改正権を同視し、いずれも万能な主権の行為であることを根拠にして憲法改正を無限界とする学説も存在する。更に法は本来、人間の社会生活に奉仕する手段であり、加えてその社会は変転してやまないものであるから、法もそれにつれて変わるべきであり、憲法改正に限界を設けることは法の本質に反するとする学説も存在する。しかし今日では、憲法改正には法的な限界があると考える学説が通説である。限界説の論拠は、①憲法制定権力が憲法を制定し、この憲法によって憲法改正権が作られるのであるから、憲法改正権が自己の存立の前提たる憲法制定権力の所在の変更することは、いわば自殺行為であって理論的に許されない、②憲法制定権力をも拘束する自然法的な根本規範があり、憲法改正権もこれに拘束されているとするなどである。要するに、憲法改正は元の憲法の存続を前提として、憲法典自体に特に全部改正を認める規定がない限り、新憲法にとって替えるとか元の憲法典との同一性を失わせるようなものは法的改正として、改正の限界を越えて不可能ということである。
日本国憲法では、この改正しえない部分としてまず国民主権を定めた規定(前文・1条後段)が挙げられる。次に、基本的人権の原理も、この原理と国民主権が個人の尊厳という基本原理によって不可分の関係にあるから改正できないと考えられている。また、憲法改正規定のうち国民投票を定めた部分は、憲法制定権力が国民にあることを具体的に現わす規定であるから、やはり改正できないと解される。さらに、一般的に平和主義の原理も改正できないとされている。もっとも、戦力不保持についての9条2項については、平和主義の解釈により必ずしもその否定に繋がるものではないとして2項の改正を可能とするのが多数説であるが、不可能とする学説も有力である。
4)憲法の変遷
憲法の変遷とは憲法改正手続を経ないで、つまり憲法の文言はそのままでありながら、憲法の意味内容が実質的に変化することをいう。もちろん、憲法の変遷についてはこの概念規定だけではなく憲法の文言はそのままにその客観的意味が変化するとか、あるいは憲法上記に違反・矛盾する憲法実例が長期にわたり繰り返され、国民一般の意識によってよって支えられるなどして憲法規範性を獲得し、当該憲法条項が改廃された結果になるとするものなどが挙げられている。もちろん、イェリネックが「事実は法を破壊し、法を創造する」と指摘したように、憲法に書かれた文言が社会の変化によって意味内容を変化させることはありえ、必要なことである。しかし、これは憲法解釈の枠の中の意味変化にすぎない。ここで問題なのは、解釈の枠を越えた意味の変化が「解釈」の名の下で行われること、つまり解釈の基準そのものが変化することである。このような問題が生じるのは外からの客観的事実認識レベルでの「社会学的意味の変遷」と枠内からの解釈学的レベルでの「法解釈学的意味の変遷」の区別が行なわれていないからである。いずれにせよ、この憲法の変遷は国家行為によって生じ、このような「違憲の」国家行為に対して憲法を改正したのと同じ法的効果を認めうるか否かが問題となる。
肯定説は慣習法の成立と同様に考えて、継続的反復と国民の法的確信を要件とし、憲法を改廃する効力を認める。この説の背後には、法学一般の議論として慣習法の成文法の改廃力が多数によって肯定されていることがある。極論として、憲法の変遷を国民の不断の憲法制定権力の行使という観点から肯定する学説もある。これに対して、否定説は違憲の国家行為はあくまで事実として行われているのであって、そのような憲法の変遷は法的性格を獲得しないとする。肯定説に対しては、①変遷が成立する時点の決定が困難であり、国民の意識が将来変わりうる、②単に違憲的国家行為が反復・継続されているにすぎないのに、これを正当化するために憲法の変遷が利用される危険性が指摘される(憲法9条など)。
(3) 公務員の憲法尊重擁護義務
憲法99条によって、天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官「その他の公務員」(国家および地方公務員)に対して憲法を尊重し擁護する義務が課されている。一般に、この義務は倫理的義務であるとされているが、一定の場合には法的義務と解される(例えば公務員の欠格事由に日本国憲法を暴力で破壊しようとしたり(国公38条、地公16条)、憲法遵守の宣誓を拒否したり積極的に破壊する行為(国公82条、地公29条)など)。
- 抵抗権と国家緊急権
すでに、中世や絶対王政期において「暴君放伐」論が理論上なされていた。これは近代立憲主義に至って、国民の信託を受けている国家権力が国民に対して重大な侵害を行い、合法的な救済方法がもはやなくなったとき、国民が権利を守るために、政府を打倒することも可能な抵抗の権利と解されるようになった。したがって、抵抗権は近代立憲主義秩序を維持することを目的とする。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言(2条)などでは抵抗権は明文で規定されていが、抵抗権について明文の規定をもたない日本国憲法の下で、抵抗権を認めることができるか否かが問題である。多数説は、現行憲法が近代立憲主義と自然権思想に基礎を置き、抵抗権は憲法に内在しているとする。ただし、抵抗権の無制限の行使は「社会契約」に基づく国家の解体に繋がるので、その行使の条件として①侵害の重大性、②不法の明白性および③行使の補充性が挙げられる(オーリウによれば、請願権→社会権→抵抗権の行使の段階が示されている)。
国家緊急権とは戦争・内乱・大規模災害などの例外的な場合に、国家自らを保持するために発動する権力であり、憲法秩序を一時的に停止して、平常時ならば違憲となる国家権力の行使が認められることをいう。一時的にせよ、国家緊急権は憲法秩序を破る行為を国家に許すものであるから、それ自体が近代立憲主義秩序に対する危険を孕んでいるというパラドックスに直面する。なお、2001年の9.11の同時多発テロを契機に国家緊急権の必要性が強調されている傾向に留意すべきである。
明治憲法には戒厳大権(14条)、非常大権(31条)などの国家緊急権に関する規定がおかれていたが、日本国憲法には明文の規定はなく、その行使が認められても①一時的かつ必要最小限度の原則および②責任性の原則の条件が充足されなければならない。また、2003-04年の武力攻撃対処関連3法、有事関連7法および国民保護法に注意が必要である。
無断転載を禁ずる