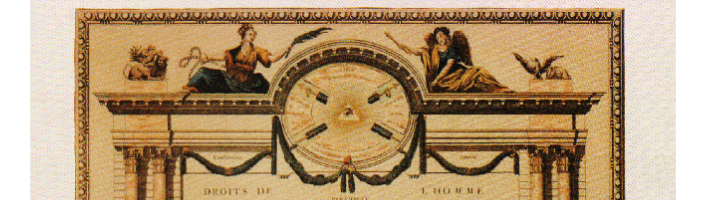土佐日記
3月8日の備忘録。
9時10分、駅前の松屋で牛めし並 280円を食べる。


12時55分、駅前の庄やで日替り〔C〕 500円を食べる。

午後から、紀貫之『土佐日記』についてレポートにまとめる。高校時代に読んだ紀貫之の印象と今回、現代語訳と対比させて通読し、解説を読んだ後のそれとは随分異なるものであった。祖父が漢学者であったこともあり、私自身も古文・漢文は得意であったが、それには、私が高校時代に日本古典文学全集を全巻通読していたことの効果が大きい(とりあえず、出典のストーリーを知っていることは大きな助けになる)。そのおかげで駿台予備校時代、古文の田中重太郎先生に最優秀答案として褒められたことがある。いずれにせよ、紀貫之も京都の中級貴族としての特権階級意識から自由でいることはできず、時代的な枠の中を越えることはできなかったという制約が理解できた。←時間ができれば、この部分の解説も後日、補完したいと考えている。
田中重太郎
田中 重太郎(たなか じゅうたろう、1917年7月7日 - 1987年5月16日)は、日本の国文学者(文学博士)。京都市出身。
立命館中学校教諭などを経て1959年に相愛女子短期大学(現相愛大学)教授。『枕草子』研究で知られ、1947年に日本古典全書(朝日新聞社)の校註を行った際より「草子」や「草紙」は元の意味に即して「冊子」と書き表すべきであるとして「枕冊子」の表記にこだわり続けた。
『枕草子』の写本が4系統存在する中で、田中自身は江戸時代に北村季吟が『枕草子春曙抄』を刊行してから大正期まで流布本の主流であった能因本に代わって昭和初期に池田亀鑑が本文解釈上の優位性を提唱した三巻本を善本とする立場より日本古典全書でも底本に三巻本を採用したが、1953年に『校本枕冊子』を刊行した際は当時の学界で依然として広く支持されていた能因本(三条西家旧蔵本)を底本として採用。1972年より『枕冊子全注釈』(角川書店)全5巻[1]の刊行を開始した際も『校本枕冊子』の本文に対する注釈を補完する観点と、過去に日本古典全書で三巻本の注釈を行った経緯より能因本を底本に採用した。
『全注釈』の刊行開始より11年目の1983年に第4巻が刊行された後、最終巻を残して1987年に逝去。享年71(満69歳没)。第5巻は鈴木弘道が田中の遺稿を基に作業を継承したが、鈴木も完成を待たず1992年に逝去し最終的に中西健治の手で完成、1995年に第1巻発売より23年を費やして完結した。田中が生前に収集した『枕草子』関連の資料群を始めとするコレクションは現在、相愛大学図書館で春曙文庫(しゅんしょぶんこ)として所蔵されている。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E9%87%8D%E5%A4%AA%E9%83%8E

(追記)
『土佐日記』を選択。
校注・訳者 菊池靖彦・木村正中・伊牟田経久『土佐日記 蜻蛉日記』〔新編 日本古典文学全集 13巻〕(小学館、1995年)
(1)についての論述
一.製作環境 木村正中によれば、『伊吉連博徳書』『難波吉士男人書』をはじめとし、帝王の起居注、宮廷の行事や公の書件の記録、官人の行動記録ないし備忘録としてできた「日記」が、時に寺院関係や僧侶の行跡、特に渡唐僧の見聞録のようなものにまで発展をしていたが、それらにはともかく記録のスタイルが一貫してあったとされる(前掲書3頁)。選択した『土佐日記』も、土佐から京への旅日記の形態をとっている点で、日記文学の流れにつながるものである。より具体的に言うならば、『土佐日記』はそれまでの『漢文日記』の系譜を継ぎながらも、和歌をふんだんにはめ込む「日記文学」を継いでいるということになろう。
二.流通 出版文化が現在のように確立されていたわけではないので、その流通のあり方は書写によるものであった。実際、作者と書名について「貫之筆」がすなわち「貫之作」を意味するのか、『土佐日記』は「土佐日記 貫之筆」ではないのかという疑問がある。菊池靖彦によれば、その現在に至る流通は以下のようなものである。第一次本と第二次本の区別は、それが原本を直接書写したものであるか、第一次本をさらに書写したものとに分かれるが、定家自身が手にした原本は小河御所に保管されていたが失われ、第一次本には定家書写本前前田育徳会尊経閣文庫に蔵されている国宝、定家の子為家が書写した為家書写本が大阪青山短期大学に所蔵され重要文化財となっている。一方、第二次本としては青谿書屋本、日本大学図書館本、三条西家本が残っている。現在、為家書写本を除く四本は複製刊行され、翻訳はすでに五本とも刊行されている(前掲書59-61頁)。
三.享受のあり方 わが国における『土佐日記』の享受のあり方は、以下のようなはやりすたれがあったとされる。
江戸時代、鹿持雅澄『土佐日記地理弁』、北村季吟『土佐日記抄』、岸本由豆流『土佐日記考証』、冨士谷御杖『土佐日記燈』、田中大秀『土佐日記解』、香川景樹『土佐日記創見』ら語訳を中心とした注訳とそれなりに有益な著作意図の探求の成果を残した『土佐日記』の研究も、明治、大正、昭和初期にはこれといった顕著な業績に乏しいとされる。ようやく、本格的な作品論が緒についたのが昭和10年代、それが盛行し始めたのが20年代で、それぞれの記念碑的業績を残しながらも、しかしなお歩みの緩かった『土佐日記』研究は、昭和30年代以後、急速に隆盛に赴いた。ことに50年代以後、叢書・全集のかたちでの注釈、評釈、口語訳が出揃ったさまはまことに壮観である、と(前掲書76-77頁)。
これとの関係で、『土佐日記』を、後続する『蜻蛉日記』以下の女流日記文学へとつないでいく方向と、『古今集』や『新撰和歌』、それに屏風歌等々を含めた貫之研究の中心に『土佐物語』を包括していく方向と、そのいずれに重要を置くのかという問題が出てくる(前掲書77頁)。
四.作者のあり方 『土佐日記』の作者である紀貫之は、この作品の中でアンビバレンツな立ち位置にある。それは「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」と宣言することによって、自らを確たる一個の人格を備えた<私>としながらも、結局は官人としての<公>の立場から離れきれない貫之の心情である。菊池によれば、冒頭の宣言は一般に「女性仮託」と言い慣わされてきたが、これは「女性宣言」と言った方が良いとされる(前掲書63頁)。
この問題を木村は以下のように要約している。
「『土佐日記』には、愛児を失った親心のごとき切々たる私的な感情と、功利的な人間に対する風刺などの社会的な批判とが、必ずしも十分に統合されずに混在し、なかなか複雑な様相を呈している。思うにそれは、貫之がこの『土佐日記』において、官人の立場から自由に解放されることを強く求めているにもかかわらず、完全に官人の立場を切り捨てることが本来彼に出来るはずがなかったことに原因する、自己矛盾の反映と見てよいであろう」(前掲書7頁)。
五.用語・文体等について これについての『土佐日記』の最たる特徴は、いうまでもなく「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」という冒頭の宣言によって「女性仮託」、すなわち、仮名文および虚偽混淆ということになる。
まず順番を入れかえるが、虚偽混淆についての説明から行うこととする。菊池によれば、以下のようになる。
「漢文ならば、語句や句の一々ごとにそれに対応する事実が問われるところを、仮名文は実も虚もならぬし、均等化してしまうのである。このように仮名文と虚実混淆とは切り離し得ないのである」(前掲書65頁)。
次に、仮名文であることの効用とは何か。
「『土佐日記』は59首の歌を含む。歌とそれにまつわる話はこの作品の生命である。歌を自由に記せること、それには仮名文であることが欠かせない。また、この作品の味わいを深めているものに、風刺や機知、そして情調としての「わびし」があるが、そうしたことが仮名文であることによってこそ実現し得ていることに注目しなければならない」(前掲書65頁)。
文体についての特徴を付け加えて説明するならば、仮名による和文書きは当然話しことばが基調になるのではないかという問題ともつながる。
「仮名による和文を書く、ということは、新しい試みであった。それは当然話しことばが基調となるはずである。しかし、それでは書き切れないということがあった。話しことばはそのままでは書きことばにはならない。したがって、その文体はいきおい訓み下し調をまじえることになる。『土佐物語』には訓読語が頻出することはこれまでに指摘され続けてきた。それは『土佐日記』の独特の文体というよりは、初期仮名文の当然あり得るすがたであろうともいわれている。それとともに、読者に語りかける意味で、物語的な語法もあることが指摘されている」(前掲書66頁)。
―以上―
(2)についての論述
以下、理解・共感できる点と、よくわからず・批判したい点に分けて論述するが、当然のことながら、それは現代人のパースペクティブから貫之の考えを測るものであることをあらかじめ指摘しておきたい。
一.理解・共感できる点について、
親子の情は、時代を超えて普遍的なものであると感じさせる歌が多く出てくる。ここでは、前掲書55-56頁の帰宅後(2月16日)、主人公が回想とともに歌を詠む場面を挙げることとする。
思ひ出でぬことなく、思ひ恋しきがうちに、この家にて生まれし女子の、もろともに帰らば、いかがは悲しき。船人も、みな子たかりてののしる。かかるうちに、なお、悲しきに堪へずして、ひそかに心知れる人といへりける歌、
生まれしも帰らぬものをわが宿に小松のあるを見るが悲しさ
とぞいへる。なお、飽かずやあらむ、また、かくなむ、
見し人の松の千歳に見ましかば遠く悲しき別れせましや
忘れがたく、口惜しきこと多かれど、え尽くさず。とまれかうまれ、とく破りてむ。
やっと、都の自宅に戻ってホッとしたときに、ふとわきあがる親心は現代人にも通じるところである。
二.よくわからず・批判したい点について、
現代人のきれいごとと言われるかもしれないが、貫之が露骨な身分差別、あるいは「みやび」の心の欠如した者に対する、すなわち「ひなびた」者に対する差別意識である。貫之自身が中級貴族に過ぎず、しかも『土佐日記』においては女性であるとしているにもかかわらずである。それは、旅の一員として彼女(貫之)が認めた歌を差し出した女性や、童との対比で明らかになる。それは、みやこ人の「特権意識」、あるいはインナーサークル的な閉じられた身内意識と、その他の者とを意識下において区別=差別する排除意識である。そのことが、明確に表現されているシーンが、前掲書35-36頁の揖取に対する態度であろう。
かくうたふを聞きつつ漕ぎ来るに、黒鳥という鳥、岩の上に集まり居り。その岩のもとに、波白くうち寄す。揖取のいふやう、「黒鳥のもとに、白き波を寄す」とぞいふ。このことば、何とにはなりけれども、ものいうやうにぞ聞こえたる。人の程にあはねば、とがむるなり。
かくいひつつ行く、船君なる人、波を見て、「国よりはじめて、海賊報いせむといふなることを思うへに、海のまた恐ろしければ、頭みな白けぬ。七十路、八十路は、海にあるものなり。
わが髪の雪と磯辺の白波といづれまされり沖つ島守
揖取いへ」。
この引用箇所の前の部分との対比が実は重要であるが、この部分の「このことば、何とにはなりけれども、ものいうやうにぞ聞こえたる。人の程にあはねば、とがむるなり」だけでも差別視していることが明確である。これを、この時代の特権階級、貴族、みやびな人の平均的考えと見るのか、今日的な見方でこれを評価するのかでは大きな差を生じることは当たり前であるが、ここではあえて批判することとした。
―以上―
評価 合格
採点 川上先生
コメントなし
2014年3月31日追記
17時43分、駅前のすき家で以下のものを注文して食べる。
牛丼並 280円
山かけオクラTP 130円
みそ汁 70円

今日のドイツ語単語
genesen 直る genas genesen
genießen 楽しむ genas genossen
geschehen 起こる geschah geschehen
gewinnen 得る gewann gewonnen
gießen 注ぐ goß gegossen