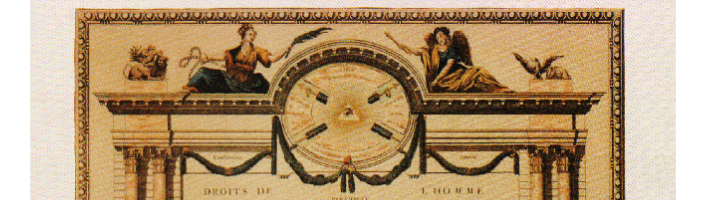月曜の振替日
11月6日の備忘録。

午前中から、お腹の調子が良くなかった。
午後4時20分から午後5時50分まで、月曜日の講義の振り替えで「法学概論」の講義を行う。
講義で取り扱ったのは、『基本的人権の事件簿』の第5事件であった。
講義内容は、学生のリアクションペーパーをいくつか挙げることにで代えることにする。
・今回の講義は「平等権」の話であったが、民法733条の話は非常に興味深かった。自分は、医学の進歩でDNA鑑定ができる今日では、6ヶ月の再婚禁止期間はいらないと思っていた。しかし、現実問題では、立法府の法律制定に時間がかかるため、違憲判決を出しにくいという事実は初耳であった。
法律の目的テスト、手段テストという概念があったが、戦前の日本には「治安維持法」などにみるように、手段がつりあっていないケースが多々あったのではないかと推測した(Tくん)。
・今回の講義では、女性の再婚禁止期間が6ヵ月と定められていることについては、これは厳格な審査のもとで定められたものではなく、期間を設けるための専門的な根拠に欠けるといった面で6ヵ月という期間が定められたことがわかった。
また、合理性の基準について考えていく中で、目的テストと手段テストの双方を踏まえて判断されるが、訴訟を起こす側も筋の通った主張を持っているという点で、目的テストで基準を満たさないといった事例は起こりにくいものであると感じた(Tくん)。
・今回の授業を聞いてやはり法律学は細かい具体的な日数や人数などを決めるのが難しい学問なのだなと思いました。何かを決めるにしても何を基準にしていいか誰の意見が正しいのかとあいまいな部分の中で決まっていることが多く、既成の法律を変えることはとても難しいことなのだろうと思います。
また、法律が目的テストや手段テスト、刑の権衡に照らしあわされて作られているというのは法律が出来上がるまでにはたくさんの手順が必要なことを改めて感じました(Sさん)。
・今日は、法律が違憲か否かという単なる判断についてだけではなく、その後法律をどのように変えていくのかというところまで学べることができたと思います。
女性の再婚禁止期間については中学生のころに習いその生物学的理由によって納得していました。しかし、6ヵ月という期間を設けることによってむしろ子どもの父親が誰であるのか判断しにくくなるという考えには驚いたし、なるほどなと思いました(Iさん)。
・今日の講義では、法律の目的と手段の基準について学んだ、結局、目的の正当性や手段の相当性の合理的な基準というのは明確には、決まっておらず、そのときそのときのケースに合わせるしかないのか?というのが気になった。また全ての法律が制定されるために細かい期間などを決めなければならないとすると、法律を決めるというのは非常に難しいなと思った。そしてとても単純な疑問だが今の民法733条で決められている6ヶ月という期間はどのように決められているのかがすこし気になった。全体的にとてもわかりやすい授業だった(Tさん)。
12時28分、大学近くの宝島でLトリプル120 714円を食べる。
以下メモ
「さて、人民が政治の主人公であり、主権者である民主主義において、なぜ憲法によって政治権力を制限する必要があるのだろうか。たとえ、公と私の区分が必要であり、人びとの権利を保障することが必要だとしても、それは民主政治を通じて十分に現実可能ではないだろうか。
この問題については、さまざまな答え方があるが、ここでは、憲法による公権力の制限を、主権者が自らの能力を拡大ないし保持するための自己拘束として捉える見方を紹介しよう。プレコミットメント(precommitment)という考え方である。
自分が非理性的に行動して自らの利益を害する危険が予想されるとき、自分の行動の幅を予め限定するという方策はしばしば見られる。これから飲酒しようとするとき、飲酒運転をしないよう、自動車の鍵を自分の信頼する友人に預けて(彼自身は飲酒しないという前提である)、決して自分に鍵を返さないでくれと頼むのがその例である。主権者がその権限の一部を独立の機関に委ねる権力分立の原理も、このプレコミットメントの一例と見る余地がある。たとえば、ジャン・ボーダンは、貨幣鋳造権が主権の一要素であるとしたが、賢明な君主は貨幣鋳造権を自分自身で行使すべきではないとした。そうすれば、彼の発行する貨幣は信用を失い、彼の政治力・財政力はむしろ低下するからである。制約された権力は、無制約な権力よりも強力だというわけである。
民主国家において、主権者であるはずの人民の政治的な決定権が憲法によって制限されているのも、そうした制限を課せられた政治権力の方が、長期的に見れば、理性的な範囲内での権力の行使を行うことができ、無制約な権力よりも強力な政治権力であるというのが、プレコミットメントという視点からの説明である。」(長谷部恭男『憲法とは何か』(岩波新書、2006年)81-82頁)
「ボーダンのプレコミットメント論については、Stephen Holmes,Passion and constraint:On the Theory of Liberal Democracy (Chicago University press,1995),Ch.4,esp.p.114参照。邦語文献では、阪口正二郎「立憲主義の展望-リベラリズムからの愛国心」自由人権協会編『憲法の現在』(信山社、2005年)や愛敬浩二「憲法によるプリコミットメント」ジュリスト1289号(2005年5月1~15日号)2頁以下に、プレコミットメントに関する分かりやすい説明がある。この論点に触れた拙稿としては、「民主主義国家は生きる意味を教えない」紙谷雅子編著『日本国憲法を読み直す』(日本経済新聞社、2000年)所収がある。」(同上・85-86頁)
「ヨーロッパでは不安定な王権の下で鋳造権が諸侯に委譲される場合も少なくなく(例えば神聖ローマ帝国の金印勅書では選帝侯に鋳造権を与えている)、貨幣発行利益を確保のためにしばしば額面を水増しした貨幣が発行されて貨幣相場は悪化した。こうした状態が解消されるには、フランスのニコラ・オレームによる『貨幣論』(1355年)における批判(貨幣の新規発行などの操作は、不安定な貨幣価値を安定させる場合にのみ許されるとする)を経て、絶対王政期以後に諸侯の没落に乗じて鋳造権を回収する必要があった。」(wiki)
これから紹介する一連の文書は、F・A・ハイエクの「貨幣発行自由化論」(1999年9月、東洋経済新報社、訳者は川口慎二)からの抜粋である。先に、その概要を知るために、訳者の「あとがき」とハイエク自身が書いた本書の序文を紹介したが、今回は、本文の第三章「貨幣創造についての政府特権の起源」を紹介しよう。
貨幣創造についての政府特権の起源
近世初頭に、ジャン・ボーダンが統治権の概念を発展させたとき、彼は貨幣鋳造権(right of coin-age)を統治権の最も重要かつ本質的な部分として取り扱っている。
註:ジャン・ボーダンについては、長谷川三知子の参議院憲法調査会での意見陳述がおおいに参考になる。
註:国民国家における貨幣鋳造権の問題については、萩原能久の説明を手がかりに勉強を始めると良い。貨幣鋳造権は、国家の特権であると誰しも疑っていないが、ハイエクはそのことに疑問を投げかけているのである。
この特権は最初から、それが公衆にとって利益であるという理由で主張され認められたものではない。それは単に政府の権力の本質的な要素として主張され認められたのである。
註:「地方にできることは地方でやればいい。」「民間にできることは民間でやればいい。」これは小泉総理の口ぐせであるが、このことは私も大賛成である。「政府信託論」が「地方分権の原則」でなければならないと思うが、「政府信託論」「地方分権の原則」からすれば、まずは「地域通貨」があって、それを補完するために「国の通貨」があるのではないか。
金属の重量と純度についての政府証明
政府が引き受けてもよいと了解されていた任務というのは、もとより最初は、貨幣を造りだすというよりも、広く貨幣として役立っていた素材---これはずっと昔から三つの金属、すなわち、金、銀、そして銅だけであったが---の重量と純度を証明するということにあったのである。これは均一の度量衡を確立し証明する任務とやや似たものと思われていたのである。
金属片はそれらが特定の権威者の刻印をもつときにのみ正式の貨幣とみなされたのである。そしてこの権威者の義務は、鋳貨にその価値を与えるために、鋳貨が正式の重量と純度をもっていることを証明することにあると考えられていたのである。
しかしながら、中世の時代に貨幣に価値を与えるのは政府の行為であるという迷信が生まれた。経験がつねにそうでないことを示していたにもかかわらず、この valor impositus(君主により決定された価値)という教義は、主として法律上の教義によって受けつがれ、それはより少ない貴金属の量を含んでいる鋳貨に、同一の価値を付与しようとする君主たちのいつも変わらぬむなしい無駄な試みを正当化するのにある程度は役立ったのである。(今世紀の初めにこの中世的教義はドイツのクナップ教授によって復活させられた。彼の『貨幣国定論』はいまなお現代の法理論にかなりの影響を与えているように思えるのである)。
民間企業がもし許されていたならば、良質でかつ少なくとも信頼に足る鋳貨を供給することができたであろうということを疑う理由はない。事実それは時に行われたのであり、あるいはまた行われるように政府によって権限が与えられていたのである。けれども均一でかつ識別可能な銭貨を供給するという技術上の任務が、いぜんとして重大な困難を示すものであるかぎり、それは少なくとも政府が行う有用な任務であったのである。残念なことに、政府は、少なくとも政府の提供する貨幣を人々が使用する以外に道がないかぎり、この任務は有用であるだけでなくまた大いに有利になされうることにすぐに気付いたのである。貨幣発行特権(seignorage)、すなわち、採鉱費用を償うために課せられる手数料は大変に魅力ある収入源であることが分かり、そしてそれはすぐに鋳貨を製造する費用をはるかに越えて増額されたのである。そしてまた新しい貨幣を鋳造するために政府の造幣所で余分な金属を保有しつづけるということから、次のことが実施されるようになるまでにはほんの一歩にすぎなかった。それは、流通している鋳貨をより少ない金・銀の含有量をもつ各種の呼称の貨幣に改鋳するために回収するということで、中世の時代にますます広まっていったのである。われわれはこれらの価値低下の結果について次章で考察することにしたい。しかし貨幣発行にかかわる政府の機能がもはやある金属片の重量および純度を単に証明するという機能ではなく、発行されるべき貨幣量を計画的に決定することを含むようになって以来、政府はこの任務に全く不適当なものとなったのである。そして無条件にいえることであるが、政府は絶え間なくまたいたるところで信頼を乱用し人々を欺いてきたのである。
紙幣の出現
政府特権は最初は鋳貨が当時用いられていた唯一の種類の貨幣であったために、鋳貨の発行にのみ適用されたのであるが、それは他の種類の貨幣が登場した時に急速にこれらの貨幣にまで拡大されるようになったのである。
これらの貨幣は当初は政府が貨幣を必要とし、それを強制借入によって調達しようとした時に生じたものであった。この借入に対して政府は受領書を与え、人々にはこれを貨幣として受け取ることを命じたのである。政府紙幣が次第に現れそして間もなく銀行券(bank note)が登場したが、このことがわれわれの目的にとってもつ意義は複雑である。というのは、長い間、異なった呼称をもった新しい種類の貨幣の出現ということが問題ではなく、政府の独占によって発行され定着している金属貨幣に対する紙に書かれた請求権を、貨幣として用いるということが問題であったからである。
紙片あるいはそれ自体はほとんど市場価値をもたない素材でできているその他の名目貨幣が徐々に受け入れられ、そして貨幣として保有されるようになるのは、それらがある価値をもつ客体に対する請求権を表しているのでなければたぶん不可能である。貨幣として受け入れられるためには、それらはまず自らの価値をなにか他の源泉、たとえば、他の種類の貨幣への交換可能性(convertibility)のようなものから引き出さねばならない。結果として、金および銀ないしはそれらに対する請求権だけが、相互に競争が行われうるような貨幣として長い間存続してきたのである。そして一九世紀における銀の価値の急激な下落以来、銀ですらも金の重要な競争者でありえなくなったのである。(金銀複本位制度(bimetalism)の可能性はわれわれのいまの問題とは無関係である。)
紙幣統制の政治的、技術的可能性
しかしながら、いたるところで紙幣が定着して以来事態は全く異なってきたのである。金属貨幣が支配的であった間は政府による貨幣発行の独占は悪であるだけであった。しかし最良と最悪の貨幣をともに提供しうる紙幣(あるいは他の名目貨幣)が政治の統制のもとにおかれて以来、政府独占は救いがたい災いとなったのである。
貨幣の独占は政府の権力を強化してきた・・・。
無制限の権力をもった民主主義政府のどれもが紙幣の価値を満足のいくようにつねに管理できるということはあまりにも疑わしいことである。とはいえ、紙幣の価値は種々異なる原則にもとづいて規制されうることは明らかである。歴史上の経験は一見、金のみが安定通貨(stable currency)を供給することができ、そしてすべての紙幣は早晩減価するにきまっているという信念を正当化しているように思われる。けれども、貨幣の価値の決定過程についてのわれわれの洞察はすべて、この先入観は分かりよいものであるが根拠のないものであることをわれわれに告げているのである。すべての種類の名目貨幣の量をその価値が望みどおりに動くように統制し、そしてこれにより名目貨幣の受領性と価値を維持するということ、このことが政府にとって政治上では不可能であるということは、同じことが技術的には可能であるということを疑う理由になるとは思えないのである。それゆえにもし許されさえすれば、本質的に異なった種々様々な貨幣をもつことがいまや可能となるであろう。
(2001.04.18 参議院憲法調査会)
いわゆる君主主権と言われるのがこの後半の定義なんですが、まずここで、ボダンは一体何でこういう定義づけをしたんだろうかということを理解しておく必要があります。これは、今ちらっと申しましたように、フランスの十六世紀というのは、宗教戦争で国内の内紛が絶えない、ほとんど国が分裂するんではないかと内側にいる人にとっては感じられるような、そういう危機の時代でございました。この危機を何とかして乗り切っていくためには、このフランスという国家の船を沈没させないようにしっかりと国家のシステムをつくり上げる必要がある。それにはまず、平たく言えば国が一つの国家としてしっかりとまとまること、それからそのかじ取りをだれがするのかということがしっかり定まっていて、しかもそのかじ取りが自由に行えるようになっていること、これが危機に際しては非常に必要なことである、これがボダンの「国家論」を書くに当たっての心構えだったわけです。
そういう観点から、君主主権の定義というものも行われております。ここには、「主権とは市民や臣民に対して最高で、法律の拘束をうけない権力である。」という、こういう定義づけがなされております。ボダン自身としては、これは今申し上げましたように、あくまでも危機を乗り切るために必要な方便という、そういう意味での定義づけをしているわけです。
ですけれども、皆さんすぐお気づきのように、これはある意味で大変危険なものを含んでおります。法律の拘束を受けない権力というものを主権者に与えた場合に、これは何でも主権者が望めば法律お構いなしに行うことができるという一種の暴君容認論になりかねないわけです。ボダンは、これについては非常にはっきりと歯どめをかけております。ボダンはこの「国家論」の中で、主権の定義と同時に正しい統治論というものを掲げておりまして、主権者といえども、つまり最高の力の持ち主といえどもこの宇宙の絶対の支配者である神に対してはしもべである。神の命令、すなわち正しい統治を行えという命令に背いたらば、たちまち天罰が下るということを言っているんです。
正しい統治というのは何なのかというと、これは彼の言うところによれば、国民の自由と財産と生命を守り保障するということなんですね。つまり、端的に言えば国民のための政治をせよと、こういう縛りがある。それに背いたときには君主、最高の権力者といえども神罰を得ずにはいられないという、そういう考え方なんです。ですから、差し当たってボダン自身の主権論の中では、これは決して闘争的な概念でもなければ暴君容認論でもない。ただし、今申し上げたように、そういう歯どめを抜きにしたらば非常に危ういというものが確かにその中にはあったわけです。