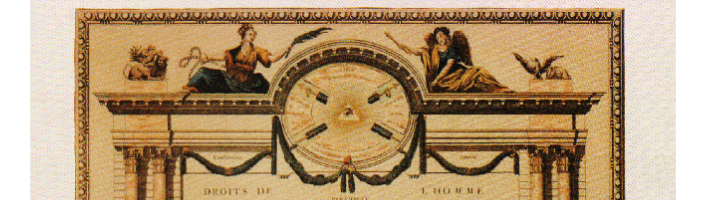百里基地訴訟
6月17日の備忘録。
午前10時半に、バスに乗って勤務大学に向かっているときに見たかわいらしい風景。
バスの中にお爺さんと、満二歳になるかならないかの赤ちゃんが乗っていた。その赤ちゃんが降車ボタンを各バス停で押すので、お爺ちゃんが「○○ちゃん、降りるバス停になったら爺ちゃんが教えてあげるから」と言って嗜めた。そうして、降車するバス停前になったとき、ピンポーンという音が鳴ったので振り返ってみると、赤ちゃんが奇声を発して身を捩って泣いている。すると、そのお爺さんが赤ちゃんに「○○ちゃんが寝ちゃったから、爺ちゃんがボタンを押してしまった」と言っていた。ほんの数秒、数分で赤ちゃんは寝てしまうのかと感心してしまう。
現代人権論/日本国憲法(担当 中野雅紀) 1013.06.18
第6講 平和主義(part03)
判例(つづき)
百里基地訴訟(最高裁第3小法廷判決平成元年6月20日)

一 国が行う私法上の行為は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には当たらない。
二 私法上の行為には憲法9条は直接適用されるものではない。
三 憲法9条の宣明する国家の統治活動に対する規範は、そのままの内容で民法90条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはなく、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、「公ノ秩序」の内容の一部を形成する。
上告理由第一点について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわない事実をまじえ、独自の見解に立つて原判決の違法をいうものにすぎず、採用することができない。
同第二点の一について
一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
1 被上告人国は、関東地区に航空自衛隊の基地を建設する必要を生じ、旧帝国海軍航空隊の訓練所の所在地で戦後開拓者が入植していた茨城県東茨城郡小川町百里原に航空自衛隊の基地を建設する計画を立て、昭和31年5月、その用地の取得につき小川町の当時の町長Cらの協力のもとにその準備を始めたところ、地元に基地建設の反対運動が起こり、開拓農民や町民の間に反対運動の団体が組織され、リコール運動が展開され、選挙の結果、昭和32年4月基地反対派の指導者であつた上告人Bが町長に当選した。被上告人国は、防衛庁東京建設部の係官を現地に派遣し、土地所有者らと折衝を重ねて次々と売買契約を成立させ、昭和33年3月ころには大部分の用地の買受けを終了した。
原判決添付第三目録一ないし四記載の土地(以下これらの土地を個別にいうときには「本件一の土地」、「本件二の土地」などといい、一括していうときには「本件土地」という。)は、基地を建設するのに不可欠な場所に存在し、これを所有していた被上告人Dは、当初基地の建設に反対し基地反対派に所属していたが、次第に反対運動に疑問を抱くようになり、昭和33年5月には、本件土地を処分して他に移転したいと考え、防衛庁東京建設部の係官の買収交渉に応ずるようになつた。
2 これに対し、上告人Bを中心とする基地反対派の者たちは、反対運動の一環として基地の建設に不可欠な土地を買い取る考えのもとに、被上告人Dとの間で本件土地につき買取交渉を進めた結果、昭和33年5月18日、同被上告人からこれを買い取ることで交渉が成立し、上告人Bの使用人で農業を営む上告人Aを買主として、代金306万円、代金支払の時期を、本件一の土地(宅地)につき所有権移転登記を経由し、かつ、本件二ないし四の土地につき農地法所定の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記を経由した時期とする約定で売買するとの契約を締結し、翌19日、右売買契約に基づいて、本件一の土地につき同日付売買を原因とする所有権移転登記を、本件二ないし四の土地につき同日付停止条件付売買を原因とする停止条件付所有権移転の仮登記をそれぞれ経由した。
ところが、上告人Aは、契約締結時に手附10万円及び右各登記を経由した日に100万円の合計110万円を支払つたのみで、残代金196万円を支払わなかつた。そこで、被上告人Dは、上告人Aに対し同年6月13日到達の内容証明郵便をもつて残代金196万円を右到達の日から10日以内に支払うよう催告し、支払わないときは右期間の経過とともに右売買契約を解除する旨の停止条件付契約解除の意思表示をした。しかるところ、上告人Aの代理人である外山佳昌弁護士らは、右期間の最終日である同月23日午後3時ころ、被上告人D方を訪れ、同被上告人に対し右残代金196万円を額面金額とする小切手を提供し、執拗に残代金として右小切手を受領するよう迫り、その結果、同被上告人はやむなくこれを残代金支払の方法として受け取つたが、右小切手は翌24日預金不足の理由で不渡りになつた。←おいおい不渡りを手形にするなよ!
3 このため、被上告人Dは、同日のうちに防衛庁東京建設部建設部長E(支出担当官)との間で売買交渉を再開し、翌25日被上告人国に対し本件土地を代金270万円(離作補償費等を含む。)で売り渡す旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、同被上告人に対し、本件二及び三の土地については同年7月1日、本件四の土地については同年12月26日、それぞれ本件売買契約に基づく所有権移転登記を経由した。そして、被上告人Dは、同年6月26日上告人Aを債務者として本件一の土地について売買契約の解除を理由として処分禁止の仮処分を得て、同日のうちにその旨の登記を経由した(以下本件売買契約とこれに先行して行われた被上告人Dの上告人Aに対する売買契約解除の意思表示を併せて「本件土地取得行為」ということがある。)。
4 上告人Bは、もともと本件土地の実質的な買主であり、したがつて、被上告人Dが上告人Aに対し本件土地についてした売買契約を解除して被上告人国との間で本件売買契約をし、右解除及び本件売買契約の効力をめぐつて本件訴訟で争われているなどの一切の事情を知悉した上で、原審係属中の昭和54年1月6日上告人Aから本件土地を買い受ける旨の契約を締結し、かつ、同年2月5日右売買契約に基づき本件一の土地について所有権移転登記を、本件二ないし四の土地については前記仮登記につき権利移転の附記登記を受けた。
二 論旨は、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」とは国の行うすべての行為を意味するのであつて、国が行う行為であれば、私法上の行為もこれに含まれ、したがつて、被上告人国がした本件売買契約も国務に関する行為に該当するから、本件売買契約は憲法9条(前文を含む。以下同じ。)の条規に反する国務に関する行為としてその効力を有しない、というのである。
しかしながら、憲法98条1項は、憲法が国の最高法規であること、すなわち、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有し、憲法に違反するその余の法形式の全部又は一部はその違反する限度において法規範としての本来の効力を有しないことを定めた規定であるから、同条項にいう「国務に関するその他の行為」とは、同条項に列挙された法律、命令、詔勅と同一の性質を有する国の行為、言い換えれば、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、したがつて、行政処分、裁判などの国の行為は、個別的・具体的ながらも公権力を行使して法規範を定立する国の行為であるから、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるが、国の行為であつても、私人と対等の立場で行う国の行為は、右のような法規範の定立を伴わないから憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当しないものと解すべきである。以上のように解すべきことは、最高裁昭和22年(れ)第188号同23年7月7日大法廷判決・刑集2巻8号801頁の趣旨に徴して明らかである。そして、原審の適法に確定した事実関係のもとでは、本件売買契約は、国が行つた行為ではあるが、私人と対等の立場で行つた私法上の行為であり、右のような法規範の定立を伴わないことが明らかであるから、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しないものというべきである。これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違憲はなく、論旨は、以上と異なる見解又は原審の認定にそわない事実に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
同第二点の二の(一)及び(二)について
論旨は、本件売買契約は、被上告人国がこれをするについての準拠法規である防衛庁設置法及びその関連法令が憲法9条に違反して無効であるから、準拠法規を欠くことになり無効である、というのである。
しかしながら、被上告人国が被上告人Dとの間で締結した本件売買契約は、国がその活動上生ずる個別的な需要を賄うためにした私法上の契約であるから、私法上の契約の効力発生の要件としては、国がその一方の当事者であつても、一般の私法上の効力発生要件のほかには、なんらの準拠法規を要しないことは明らかであり、したがつて、本件売買契約の私法上の効力の有無を判断するについては、防衛庁設置法及びその関連法令について違憲審査をすることを要するものではない。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、これと異なる見解又は原審の認定にそわない事実に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
同第二点の二の(三)について
論旨は、被上告人国の代理人として本件売買契約を締結したEは、組織規範である防衛庁設置法及びその関連法令が憲法9条に違反して無効であることによつて、被上告人国の支出担当官としての職務権限を欠くことになるから、本件売買契約は、結局無権限者のした行為として私法上無効である、というのである。
しかしながら、売買契約の当事者本人が、現にその契約締結行為を行つた者の代理権限の存在を認めている場合には、第三者が、右契約が無権限者のした行為であると主張してその契約の効力を争うことはできないというべきところ、本件訴訟において、被上告人国は、Eが被上告人国の代理人としてした本件売買契約が本人である被上告人国と相手方である被上告人Dとの間で有効に成立したと主張しているのであるから、第三者である上告人らは、右理由による無効を主張することはできず、したがつて、Eが本件売買契約の締結当時必要な職務権限を有していたか否かについて判断する必要はない。これと結論を同じくする原審の判断は首肯することができる。論旨は、これと異なる見解に立つて原判決を論難するか、又は判決の結論に影響のない原判決の説示部分の違法をいうものであつて、採用することができない。
同第三点について
論旨は、本件売買契約は国がその一方当事者として関与した行為であるから、私人間で行われた私法上の行為と同視すべきものではないが、仮に私人間で行われた私法上の行為と同視しうるものであるとしても、憲法の保障する平和主義ないし平和的生存権に違反し、かつ、憲法9条が直接適用され、これに違反する、というのである。
しかしながら、上告人らが平和主義ないし平和的生存権として主張する平和とは、理念ないし目的としての抽象的概念であつて、それ自体が独立して、具体的訴訟において私法上の行為の効力の判断基準になるものとはいえず、また、憲法九条は、その憲法規範として有する性格上、私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではなく、人権規定と同様、私法上の行為に対しては直接適用されるものではないと解するのが相当であり、国が一方当事者として関与した行為であつても、たとえば、行政活動上必要となる物品を調達する契約、公共施設に必要な土地の取得又は国有財産の売払いのためにする契約などのように、国が行政の主体としてでなく私人と対等の立場に立つて、私人との間で個々的に締結する私法上の契約は、当該契約がその成立の経緯及び内容において実質的にみて公権力の発動たる行為となんら変わりがないといえるような特段の事情のない限り、憲法9条の直接適用を受けず、私人間の利害関係の公平な調整を目的とする私法の適用を受けるにすぎないものと解するのが相当である。以上のように解すべきことは、最高裁昭和43年(オ)第932号同48年12月12日大法廷判決・民集27巻11号1536頁(三菱樹脂事件)の趣旨に徴して明らかである。←このあと、三菱樹脂事件が繰り返し言及されることに注意。
これを本件についてみると、まず、本件土地取得行為のうち被上告人Dが上告人Aに対してした契約解除の意思表示については、私人間でされた純粋な私法上の行為で、被上告人国がなんら関与していない行為であり、しかも、被上告人Dは、上告人Aが売買残代金を支払わないことから、上告人Aとの間の売買契約を解除する旨の意思表示をするに至つたものであり、かつ、被上告人国とは右解除の効果が生じた後に本件売買契約を締結したというのであるから、被上告人Dのした売買契約解除の意思表示は、被上告人国が本件売買契約を締結するについて有していた自衛隊基地の建設という目的とは直接かかわり合いのないものであり、したがつて、憲法9条が直接適用される余地はないものというべきである。←そもそも、期日までの支払いをしなかったことが問題では。もっとも、支払っていたら事件性があったのか、という更なる疑問が発生するのではあるが。
次に、被上告人Dと被上告人国との間で締結された本件売買契約について憲法九条の直接適用の有無を検討することにする。原審の確定した前記事実関係によれば、本件売買契約は、行為の形式をみると、私法上の契約として行われており、また、行為の実質をみても、被上告人国が基地予定地内の土地所有者らを相手方とし、なんら公権力を行使することなく純粋に私人と対等の立場に立つて、個別的な事情を踏まえて交渉を重ねた結果締結された一連の売買契約の一つであつて、右に説示したような特段の事情は認められず、したがつて、本件売買契約は、私的自治の原則に則つて成立した純粋な財産上の取引であるということができ、本件売買契約に憲法9条が直接適用される余地はないものというべく、これと同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違憲はなく、論旨は、以上と異なる見解又は原審の認定にそわない事実に基づいて原判決を論難するものであつて、採用することができない。
同第四点について
論旨は、憲法9条の規定ないし平和的生存権の保障が私法上の行為である本件売買契約に直接適用されないとしても、右規定等は民法90条の定める公序の内容を形成し、右規定等に違反する本件売買契約を含む本件土地取得行為は、結局公序良俗違反として無効である、というのである。
本件売買契約は、前述のように、被上告人国が自衛隊基地の建設を目的ないし動機として締結した契約であつて、同被上告人は被上告人Dに対しこの契約を締結するに当たつて右の目的ないし動機を表示していることは明らかであるから、右の目的ないし動機は本件売買契約等が公序良俗違反となるか否かを決するについて考慮されるべき事項であるということができるので、以下自衛隊基地の建設という目的ないし動機によつて、本件売買契約等が公序良俗違反として無効となるか否かについて判断する。
まず、憲法9条は、人権規定と同様、国の基本的な法秩序を宣示した規定であるから、憲法より下位の法形式によるすべての法規の解釈適用に当たつて、その指導原理となりうるものであることはいうまでもないが、憲法9条は、前判示のように私法上の行為の効力を直接規律することを目的とした規定ではないから、自衛隊基地の建設という目的ないし動機が直接憲法9条の趣旨に適合するか否かを判断することによつて、本件売買契約が公序良俗違反として無効となるか否かを決すべきではないのであつて、自衛隊基地の建設を目的ないし動機として締結された本件売買契約を全体的に観察して私法的な価値秩序のもとにおいてその効力を否定すべきほどの反社会性を有するか否かを判断することによつて、初めて公序良俗違反として無効となるか否かを決することができるものといわなければならない。すなわち、憲法9条の宣明する国際平和主義、戦争の放棄、戦力の不保持などの国家の統治活動に対する規範は、私法的な価値秩序とは本来関係のない優れて公法的な性格を有する規範であるから、私法的な価値秩序において、右規範がそのままの内容で民法90条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはないのであつて、右の規範は、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、民法90条にいう「公ノ秩序」の内容の一部を形成するのであり、したがつて私法的な価値秩序のもとにおいて、社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立しているか否かが、私法上の行為の効力の有無を判断する基準になるものというべきである。←一応、この講義では平和主義に冠する判例の検討なので、この部分は説明のコンテクスト上重要。確認しておくべきこと、憲法秩序における基本価値と私的な価値秩序の段階構造について。
そこで、自衛隊基地の建設という目的ないし動機が右に述べた意義及び程度において反社会性を有するか否かについて判断するに、自衛隊法及び防衛庁設置法は、昭和29年6月憲法九条の有する意義及び内容について自衛のための措置やそのための実力組織の保持は禁止されないとの解釈のもとで制定された法律であつて、自衛隊は、右のような法律に基づいて設置された組織であるところ、本件売買契約が締結された昭和33年当時、私法的な価値秩序のもとにおいては、自衛隊のために国と私人との間で、売買契約その他の私法上の契約を締結することは、社会的に許容されない反社会的な行為であるとの認識が、社会の一般的な観念として確立していたということはできない。したがつて、自衛隊の基地建設を目的ないし動機として締結された本件売買契約が、その私法上の契約としての効力を否定されるような行為であつたとはいえない。また、上告人らが平和主義ないし平和的生存権として主張する平和とは理念ないし目的としての抽象的概念であるから、憲法9条をはなれてこれとは別に、民法90条にいう「公ノ秩序」の内容の一部を形成することはなく、したがつて私法上の行為の効力の判断基準とはならないものというべきである。←平和的生存権は抽象的な権利に過ぎない。では、具体的な権利になりうるのか。
そうすると、本件売買契約を含む本件土地取得行為が公序良俗違反にはならないとした原審の判断は、是認することができる。論旨は、これと異なる見解に立つて原判決を論難するか、又は原判決の認定にそわない事実に基づいてその違法をいうものであつて、採用することができない。
よつて、民訴法396条、384条1項、95条、89条、93条に従い、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。←以下の判決文は、憲法を深く勉強したいという学生だけが読んでください。
本件は、その訴訟の対象が土地の売買契約の効力の有無という私法上の問題でありながら、買主たる国が当該土地を自衛隊の基地の建設という目的で取得したものであるところから、憲法前文及び9条をめぐつての論点が提起された訴訟である。私は、法廷意見の判示するところに異論がないが、事件の性質に鑑み、憲法上の論点を含め、若干の点について補足をしておくこととしたい。
一 論旨(上告理由第二点の一)は、原判決が国の行つた私法上の行為である本件土地の売買契約は憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に当たらないとした判断を誤りとするものであり、ここで憲法の右条項の解釈が問題となる。
(1) 「国務に関するその他の行為」という表現は、その意味が必ずしも明確とはいえないが、憲法98条1項の文理、それが最高法規と題する章におかれていることからみて、法廷意見の説示するとおり、憲法が成文法の国法形式として最も強い形式的効力を有するという実定成文法体系において憲法が最高の法規であるとの法意が示されていると解されるから、そこでいう「国務に関するその他の行為」は、例示される法律、命令、詔勅のように法規範として国の実定法秩序の一環をなすものを定立する行為を意味し、およそ国の行う行為のすべてを意味するものではないというべきである。そうであるとすると、行政処分や裁判は具体的な国の行為であるから、それに含まれないと解する余地があるが、当裁判所は、それらが国務に関する行為に該当することを承認している(最高裁昭和22年(れ)第188号同23年7月7日大法廷判決・刑集2巻8号801頁→再三出てくるから確認しておいた方がよい)。これは、行政処分や裁判のように具体的な事案に対する国の行為は、当該事案に対する措置という個別的な側面とともに、それを通じて法規範の定立という意味をもつものであり、そこでこれらも国の法体系の段階構造のうちの最下位にあるとはいえ、実定法秩序の一環をなすものとしての位置づけをもちうるのであつて、その限りで国務に関する行為に当たると解するのである。このように考えると(反対解釈)、本件売買契約のような国の私法上の行為は、右のような意味での法規範の定立を伴うものではなく、憲法98条1項にいう「国務に関するその他の行為」に該当するものとは解されず、原判決に所論の違法はないというべきである。なお、最高裁昭和47年(行ツ)第75号同51年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁(三菱樹脂事件)は、その判示のうちに、右条項にいう国務に関する行為を「国権行為」と表示している。その意味は必ずしも明確ではないが少なくともそれが国の私法上の行為を含まないと解していることは明らかである。
(2) 右のように右条項が法規範の定立行為をとらえて憲法の最高法規性を意味しているものとすれば、そこで法律その他が「効力を有しない」ということもそれらが違憲の限度で法規範としての本来の効力を有しないとするものと解される。例えば行政処分が憲法に反するということによりつねに絶対的に無効となるのではなく、行政処分は重大かつ明白な瑕疵がある場合に無効となるとされるが、憲法に反することは重大な瑕疵があるといつても、つねに明白な瑕疵とはいえず、憲法の解釈いかんによつて違憲かどうかがきめられることが少なくないのであつて、具体的な行政処分は、違憲であつても、当然無効の場合もあれば、当事者の主張によつて取り消される場合、相対的な無効の場合もありうると解される。裁判についても同様であり、ここではいつそう当然無効とされる場合は少なく、法定の手続にそつて裁判の効力が失わしめられるにとどまると考えられる。法廷意見が「法規範として本来の効力を有しない」というのは、このように違憲が直ちに当然無効とならないことを示すものであり、国務に関する行為が行政処分や裁判のような具体的な法規範定立行為を含むと解する以上、効力を有しないという規定を右のように解するのが相当である。なお、右にあげた昭和51年4月14日大法廷判決も、98条1項を引用しつつ、憲法に反する国権行為がつねに当然無効となるという考え方を否定していることも参照されてよいであろう。
二 右のように考えると憲法98条1項の規定は国の私法上の行為に及ばないと解されるが、このことは、国の行う私法上の行為のすべてが、私人の行為と同じであり、憲法の直接的規律を受けないということではない。憲法的規律がどこまで及ぶかは、憲法98条1項に関する問題ではなく、憲法という法規の性質からみてその射程範囲がどこまでか、その名宛人はなんびとかという問題である(『基本的人権の事件簿』での平和的生存権における棟居快行先生の説明が参考になる)。この観点からは、私人間の私法上の行為であつても、憲法の規律が直接に及ぶと解することも可能であるし(いわゆる憲法の第三者効力の問題であるが、最高裁昭和43年(オ)第932号同48年12月12日大法廷判決・民集27巻11号1536頁は、憲法14条、19条についてこれを消極に解している)、また国が主体でなくとも、私人を主体とする行為も一定の条件のもとに国の行為とみなして、その私法上の行為について憲法の適用を認めることもありうる(いわゆる「ステート・アクシヨンの法理」参照)。同様に国の私法上の行為も憲法の直接の規律を受けることがありうるのである。当裁判所は地方公共団体が地鎮祭のための神官への報酬などの費用を支出したことの憲法適合性を審査しているが(最高裁昭和46四(行ツ)第69号同52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁)、この支出行為は私法的な行為に基づくものとみられるから、右の趣旨を前提としているものと解することができる。そして、私見によれば、国の行為は、たとえそれが私法上の行為であつても、少なくとも一定の行政目的の達成を直接的に目的とするものであるときには、それ以外にどこまで及ぶかどうかはともかくとして、私法上の行為であることを理由として憲法上の拘束を免れることができない場合もありうるものと思われる。←伊藤裁判官は「英米法」の学者であることに注意。
しかし、右のような憲法の射程範囲を考える場合にみのがしてはならないことは、私法上の行為が憲法の規定に反するという瑕疵をもつ場合にも、直ちにその私法的効力が否定されるわけでないことである。もとより国の行為が憲法に反する以上はその効力を否定する要請が働くけれども、他方で、私法上の行為であるから私的自治の原則が認められ、私法上の行為によつて生ずる私人の権利や利益が私人の予期しない事由によつて損なわれることがないように配慮する必要があり、このような取引の安全保護の見地からは、私法上の効力を肯定する要請が働くことになる。このような点を較量しながら私法上の行為について判断することとなる。
三 憲法の諸規定は、憲法の性質上、原則として私法上の行為に直接の適用がないとしてもすべての憲法規範がそうであるとはいえず、その規定のうちには私人間で行われた私法上の行為であつても直接に拘束を及ぼすものがあると考えてよい。→以下具体例を列挙。例えば、奴隷的拘束を受けない自由(18条前段)や勤労者の基本権(28条)は、それらの規定に反する私的な行為は民法90条の公序違反としてその効力を否定する考え方もとれなくはないが、むしろ現代社会においては人を奴隷的拘束におく私人間の契約や、勤労者の団結権などの基本権を違法に制限する私的な行為は、直接に憲法に反すると判断してよいと思われる。もしそうであれば、これらは、国の私法的行為についても当然に妥当するであろう。
それでは憲法9条は、所論(上告理由第三点)のように私的行為に対して直接適用される規定と解釈すべきであるか。同条は、日本国憲法の基盤をなす平和主義の原理を正文のなかの一箇条として規範化したものであり、きわめて重要な規定であることはいうまでもないが、それは、国の統治機構ないし統治活動についての基本的政策を明らかにしたものであつて、国民の私法上の権利義務と直接に関係するものとはいえない。所論は、憲法前文及び九条の規定から平和的生存権を保障するとの解釈を抽出して、その侵害をいうが、平和的生存権をいうものの意味内容は明確ではなく、それが具体的請求権として、あるいは訴訟における違法性の判断基準として、裁判において直接に国の私法上の行為を規律する性質をもつものではないと解するのが相当である。また所論は、自由権や平等権の諸規定は間接適用されるものであるとしても、憲法9条はその法意や位置づけからみてそれらの人権規定と異なつて直接に適用されるというが、私見によれば、そのような考え方はとるべきでなく、前述の昭和48年12月12日の当裁判所の判例の判示するように憲法第三章の基本的人権の保障のような個人の権利自由にかかわる諸規定が間接適用にとどまるものとすれば、その趣旨からいつて、憲法9条が裁判規範たる性質をもつものであるとしても、統治活動にかかわる同条は、もとより国と国民との間の私法上の行為に直接に適用されるに由ないものというほかはない。
四 本件土地の売買契約に対して憲法9条の直接の適用がないとしても、同条の規定は民法90条にいう公序をなし憲法九条に違反した動機目的によつて締結された本件契約は公序違反として私法上無効であるという論旨(上告理由第四点)については、法廷意見の述べるところにとくに附加するところはないが、若干の私見を述べておきたい。
(1) 憲法は国の基本的秩序を定めているものであるから、それは当然に民法90条にいう公序の一部をなすものといえる。当裁判所が私的な会社における男女の定年について五年の格差のあることを公序に反すると判示しているが(最高裁昭和54年(オ)第750号同56年3月24日第三小法廷判決・民集35巻2号300頁)、そこに憲法14条1項が引用されていることからみても、憲法の規律するところが民法上の公序をなすことを示唆しているものと思われる。憲法9条の規定は統治機構、統治活動に向けられた政治的色彩の濃い規範であるとしても、それがために公序と関係がないとはいえず、むしろ憲法秩序として重要なものであるから社会の公序を形成しているといえるであろう。
しかし、法廷意見も説示するように、私法的な価値秩序と直接の関係のない憲法規範は、そのままの内容で私法上の秩序のなかに移されて、これに反する私法上の行為を直ちに無効とするものではないと解すべきであり、すでに憲法の射程範囲について論じたところと同様に、ここでも憲法上の規律は、私法上の価値秩序との相関関係において相対化され、そのうえで民法90条のもとでの私法上の効力の存否を判断しなければならないことになる。とくに憲法9条のような統治機構や統治活動に密着するきわめて公法的性格の強い規範の場合にそう考えるべきである。
この二つの関係を<原則>と<例外>関係として考えるのかは、さらなる検討の必要がある。
(2) 右の観点にたつてみるとき、本件土地の売買契約は、民法90条の公序違反として私法上の効力を否定するだけの反社会性をもつ行為といえるか。本件契約の目的動機として自衛隊基地の建設ということが表示されているが、これが私法的な価値秩序のもとでどのような反社会性をもつかは、憲法九条の規定について互いに対立して存在する複数の解釈のうちのいずれが正当なものかを決したうえですべき判断とは必ずしもいえないのであつて、同条の解釈について国民各層にどのような解釈が存しているかという社会的状況、自衛隊が現実に存在していること及びその活動に対する社会一般の認識などの実情に即してえられるところの社会通念に照らして、私法的な価値秩序のもとでその効力を否定されるだけの反社会性を有するかどうかで判断されるべきものであると考えられる。もとよりこのことは、憲法が国の基本構造を形成していることからみて、裁判所の判断が社会の実情にそのまま依存し追従すべきであるというのではないが、このような憲法的規律を考慮に容れてもなお、本件契約が民法90条に違反しないとした法廷意見の理由づけは正当であるというべきである。
(補足)
参考文献としては、栗城寿夫「憲法の現実化と裁判所--百里基地訴訟最高裁判決〔平成1.6.20〕を契機として」『ジュリスト』942号(1989年)p.48-53.