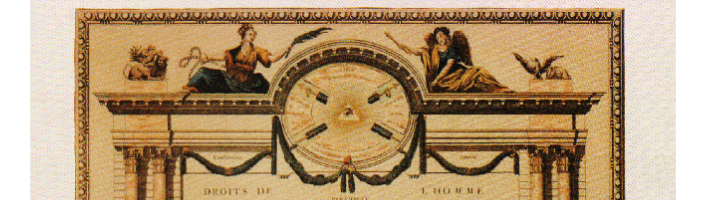金曜日
11月8日の備忘録。
お昼ご飯は、近くのマクドナルドでグラコロ、マックダブルを買ってきて、部屋で食べて済ます。


ま~、特記すべきはポケモンカレンダー(350円)を店員が薦めたので、つい買ってしまったことであろうか。

夕食は午後6時過ぎに食べたのであるが、久しぶりに午後10時前にセブン-イレブンに行ってカットフルーツミックスを買ってきて食べる(美味)。
明日の学会報告のために、総合講座は欠席した。すでに、12回のうち今日で7回目であるが、すでに4回休んだことになる。しかし、背に腹は代えられないので下記のような報告用のレジュメを仕立て上げた。問題となったのは、プリンターの調子が悪く、なかなか上手く印刷ができなかったということであろう。しかし、時間もすでに9日の午前1時を回っていたので、不満足であるが、一応のケリをつけて都合10頁のレジュメを印刷した。
ジャン・ボーダンの国家の貨幣鋳造権といわゆる“プレコミットメント”理論について
中野雅紀(茨城大学教育学部准教授)
ジャン・ボーダンが君主主権論において国王の貨幣鋳造権について論じていることは有名で
ある。そして、ボーダンが、貨幣鋳造権が国王の専権であることを認めつつも、貨幣鋳造権の濫
用を控えることを解いていることも、長谷部恭男教授の紹介などにより、法制史のみならず憲
法の研究家に広く知られるようになってきた。長谷部教授のボーダン理論の紹介は、いわゆる
「プレコミットメント」の説明のためのものである。しかし、その紹介におけるボーダンにつ
いての記述はわずかなものである。今回の報告は、つたないながらボーダンの原著を読みつつ、
長谷部教授の引用箇所を原典の前後のコンテクストから捉えなおすことを目的とする。
Ⅰ.問題の所在
果たして、長谷部教授の説明だけでジャン・ボーダンの国家の貨幣鋳造権といわゆる“プレコミットメント”理論のつながりを理解することが可能であるのか。
「さて、人民が政治の主人公であり、主権者である民主主義において、なぜ憲法によって政治権力を制限する必要があるのだろうか。たとえ、公と私の区分が必要であり、人びとの権利を保障することが必要だとしても、それは民主政治を通じて十分に現実可能ではないだろうか。
この問題については、さまざまな答え方があるが、ここでは、憲法による公権力の制限を、主権者が自らの能力を拡大ないし保持するための自己拘束として捉える見方を紹介しよう。プレコミットメント(precommitment)という考え方である。
自分が非理性的に行動して自らの利益を害する危険が予想されるとき、自分の行動の幅を予め限定するという方策はしばしば見られる。これから飲酒しようとするとき、飲酒運転をしないよう、自動車の鍵を自分の信頼する友人に預けて(彼自身は飲酒しないという前提である)、決して自分に鍵を返さないでくれと頼むのがその例である。主権者がその権限の一部を独立の機関に委ねる権力分立の原理も、このプレコミットメントの一例と見る余地がある。たとえば、ジャン・ボーダンは、貨幣鋳造権が主権の一要素であるとしたが、賢明な君主は貨幣鋳造権を自分自身で行使すべきではないとした。そうすれば、彼の発行する貨幣は信用を失い、彼の政治力・財政力はむしろ低下するからである。制約された権力は、無制約な権力よりも強力だというわけである。
民主国家において、主権者であるはずの人民の政治的な決定権が憲法によって制限されているのも、そうした制限を課せられた政治権力の方が、長期的に見れば、理性的な範囲内での権力の行使を行うことができ、無制約な権力よりも強力な政治権力であるというのが、プレコミットメントという視点からの説明である。」(長谷部恭男『憲法とは何か』(岩波新書、2006年)81-82頁)
では、上述の記述の参照文献に当たる【文献解題】で、両者の関連を理解することが可能なのであろうか。
「ボーダンのプレコミットメント論については、Stephen Holmes,Passion and Constraint:On the Theory of Liberal Democracy (Chicago University press,1995),Ch.4,esp.p.114参照。邦語文献では、阪口正二郎「立憲主義の展望-リベラリズムからの愛国心」自由人権協会編『憲法の現在』(信山社、2005年)や愛敬浩二「立憲主義の展望-リベラリズムからの愛国心」ジュリスト1289号(2005年5月1~15日号)2頁以下に、プレコミットメントに関する分かりやすい説明がある。この論点に触れた拙稿としては、「民主主義国家は生きる意味を教えない」紙谷雅子編著『日本国憲法を読み直す』(日本経済新聞社、2000年)所収がある。」(同上・85-86頁)
なるほど、長谷部「民主主義国家は生きる意味を教えない」、阪口「立憲主義の展望-リベラリズムからの愛国心」および愛敬「立憲主義の展望-リベラリズムからの愛国心」を読むことで憲法学におけるプレコミットメント論の概要を理解することができ、また、Stephen Holmes,Passion and Constraint:On the Theory of Liberal Democracy (Chicago University press,1995),Ch.4,esp.p.114を読むことで「国王の権力が最高の権力であり、不可分・不可譲であるとの君主主権を展開、君主国家の理論的裏づけを行うという役割を果たした」ボーダンが貨幣鋳造権についてSelf-bindingを唱えていることは理解できる。しかし、長谷部教授のボーダンの説明はHolmes著作の内のボーダンLes six livre de la republique 英訳版のThe Six Bookes of a Commonweal,ed.K.D.McRae,(Cambridge:Harvard University Press, 1962)に記述を負っている。そして話を複雑にするのは、長谷部の憲法学で特徴的なことのひとつとして、伝統的学説・判例理論をあえて「読み替え」ることによる正当化が挙げられる点である。たしかに、Holmesの引用箇所においては貨幣鋳造権(right of coin-age)の自己抑制(self-enforcing restriction)の話は出てくるが、プレコミットメント(precommitment)なる語は一言も出てこない。結果的に、right of coin-age→self-enforcing restriction→Public credit is a vital resource for the crownの論理的流れがプレコミットメント理論と同じであったと解釈することも可能であろう。
確かに、法律学においては行間を読む作業は大切であり、書かれていない内容を近接領域の学問的蓄積から読み取る必要性がある。しかし、この部分はわたしの勉強不足もあり、十分に理解することができなかった。今回のこの報告のために、プレコミットメント理論を再度研究して分かったことであるが、このプレコミットメント理論は経済学や社会心理学から発生したものである。したがって、まず改めてプレコミットメント理論とは何かを概観し、次にジャン・ボーダンの国家の貨幣鋳造権論を概観し、最後に両者のつながりについての私見を示したい。
Ⅱ.プレコミットメント理論とは何か
憲法の政治経済学
1980年代になって、憲法の政治経済学という言葉が使われるようになった。最初にそれを使用したのはリチャード・マッケンジーで、それまで公共選択理論の枠組みのなかで行われていた一連の研究をconstitutional economicsという言葉で使い始めたとされる(川村晃一「憲法の政治経済学」川中豪編『新興民主主義の安定』調査報告書 アジア経済研究所2009年、51頁)。その後、ジェイムズ・ブキャナンが経済学辞典のなかで「憲法の経済学」という項目を書き、1990年にはConstitutional Political Economyが創刊され、この学問領域が確立した。
ブキャナンによれば、憲法の政治経済学が対象とするのは、ルールの動的特性であり、個々人が相互行為をおこなう制度であり、これらのルールや制度が選択され、生まれるプロセスであるとされる。また、憲法の政治経済学と古典的経済学の違いは、後者が「制約のなかでの選択」を研究対象にするのに対し、前者が「制約をめぐる選択」をその対象としている点である。一方、憲法の政治学との違いは、それが対立の側面に注目するのに対し、憲法の政治経済学は協力の側面に注目している点にある(James M Buchanan“The Domain of Constitutinonal Economics” Constitutional Political Economy1(1):p.1-18)。
さらに、憲法の政治経済学の特徴は、制度を分析の中心に置いていることと、憲法を契約と捉える考え方である(Brennan and Hamlin,“Constitutional Political Economy:The Political Philosophy of Homo Economics?” Constitutional Political Economy3(1)p.280-303.)。憲法の政治経済学において、憲法は「公式の、かつ法的な憲法(成文であろうが不文であろうが)だけを含むのではなく、社会のなかで作用するその他の確立した社会的規範や慣習を含む」と定義され、ホッブズやルソー等の古典的政治思想家が唱えてきた「社会契約論」と同じ系譜に連なるとされている(p.287)。
もちろん、このような契約論的憲法論に対してはさまざまな批判が加えられてきたが、それらの論争を通じて、憲法についての研究は経済学、政治学、法律学などの複数の学問領域が交差する地点に位置するようになり、また方法論も経済学や政治経済学における合理的選択論、ゲーム理論から、地域研究、事例研究、歴史研究さらには政治思想研究までその射程に収めるものとなっている。
プレコミットメントとしての憲法
ところで、憲法を「社会契約的」に理解した場合、以下の二つの問題に直面することになる。
- 世代交代の問題
仮に、憲法が社会全員の合意に基づいて制定されたとしても、その憲法に合意した世代の人々は次第に世を去り、社会は次世代の人々へと受け継がれていくことになる。この次世代の人々は前の世代の人々が合意した憲法の下で生活していくことになるが、彼ら自身はその憲法に合意したことはない。彼らは生涯、契約した覚えのない憲法に拘束されることになる。どのようにして、憲法はその憲法の制定に関与した人々だけではなく、その後の世代の人々を拘束することを正当化するのであろうか。
- 自己拘束の問題
一般論として、憲法は民主主義の持続にとって必要だと言われている。それではなぜ
国民が主権者として自己決定がおこなえる民主主義体制において、主権者自身を拘束する憲法を制定する必要性があるのであろうか。民主政治を通じて、国民の権利保障も十分に実現されるのではないか。そもそも主権者が自らを自己拘束しても、全能の主権者はいかなる拘束も無視して、その拘束を解くことが可能ではないのか。
この大きく分けると2つの問題に収斂される難問に応えようとするのが、プレコミットメント理論である。愛敬教授によれば、ブレコミットメントとは「予め将来における選択肢を減らしておくことで、将来の出来事をコントロールしようとする」人間の行動のことである(愛敬・前掲2頁)。愛敬教授は、Elsterの論文で例示されるオデュッセウスの魔女セイレンの誘惑に打ち勝つ方法をもってプレコミットメント論を説明する。その説明の概要は以下のようなものである。旅の途中、オデュッセウスはセイレンの住む島の近くを航行することになる。このセイレンの歌声を聴いた者は、その魅惑的な声に引き寄せられ、船は座礁し二度と故郷に戻れなくなってしまう。この誘惑に負けてしまうと考えたオデュッセウスは一計を立て、部下に対して自分がセイレンの歌の魅力に負けて縄を解くように命令した場合には、より一層強く縄を締め上げるように命じた。一見すると、このオデュッセウスの行為は不合理であるが、自らの「意思の弱さという問題を抱える合理的主体が自らの自律性を損なうことなく、継続的な合理性を獲得する主要なテクニックである」とする。すなわち、プリコミットメントとは、将来強い欲求に襲われることを事前に見通して自らを拘束することを指す。勝てそうもない誘惑がまだ遠くにある安全なうちに、選択肢を狭めておくのだ。割らないとお金の取り出すことのできないブタの貯金箱など、その典型であるだろう。反対に言えば、一番危険なのは、誰でも自分は利口だから環境になんか影響されてないと考えていることである。
この議論自体は、約10年前の自民党主体の憲法改正の議論の盛んなときに語られたから、その文脈での愛敬教授の議論を続けて紹介すれば以下のようになる。
このような一般的な意味でなら、「プリコミットメント」なるものを、「継続的な合理性を獲得する主要なテクニック」(愛敬『改憲問題』(ちくま新書)102頁)として個人も国家も採用していることは誰も否定しないだろうとしている。このようにして、愛敬教授は元来、倫理・道徳・法の領域を問わず、諸規範の分析と説明の枠組みであったプリコミットメントを実定憲法解釈の手法として採用した。すなわち、彼はプリコミットメント論を媒介にして、立憲主義(≒硬性憲法)と民主主義(≒国民主権)の統合として現行憲法を再構築しようする。「プリコミットメント論によって憲法を正当化する議論の多くは、民主主義を単なる多数決とは理解せず、熟慮と討議の過程(deliberative democracy)と理解している」「プリコミットメント論は、「硬性憲法=立憲主義」を「持続可能で討議的な自己統治=民主主義」を可能にする装置・技術と解することで、立憲主義と民主主義を調和させる」(111-112頁)。
では、国民の多数意思をもってしても容易く改定されない憲法の条規;民主主義や国民主権を根拠にした憲法改正をも制約するという憲法論的なプリコミットメントとは一体どのようなものなのか? それは、立憲主義やそもそも硬性憲法の本性とどう違うというか? そして、改憲派からの「現行憲法=不磨の大典」批判への再批判、「時代に合わせた憲法の改正を求める国民主権論からの改憲論」への反論として本章で展開されるプリコミットメント論とはいかなる内容を備えているのだろうか?
問題となるのは、憲法のある規定を、事前に自己の行為の可能な範囲に制限を設けるプリコミットメントとして理解することで、民主主義や国民主権の理念をも凌駕する効力が当該の憲法規範に付与されるとなぜ言えるのかという一点に収斂する。換言すれば、憲法9条は民主主義と国民主権を根拠とした国民の改正意思に再考を促すに足るプリコミットメントなるものか否か;憲法9条を制定した「前世代」の意思が「現世代」の改正要求を阻むことをプリコミットメント論が正当化できるとなぜ言えるのか。
愛敬教授は、一般的なプリコミットメント論を実定憲法解釈の手法に読み替えることにより、自身の「憲法解釈の方法としてのプリコミットメント論」の妥当性を説明しようとする。それによれば、この読み替えの前に立ちはだかった最初の難局は、前世代の意思が現世代の改憲の欲求をなぜ阻止できると言えるのか、という問題である。
「この難局を抜ける一つの方法は、憲法を単なる自己統治に対する制約としてではなく、より持続可的で討議的な自己統治を可能にする手段・制度として描写することである」。前世代(X)が設定した憲法によって現世代(Y)の「より善い自己統治」が可能になると説明できれば、「少なくともYが自己統治(=民主主義)の価値を根拠にして、憲法を攻撃することはできなくなるからである」(104-105頁)、なぜならば、「憲法的自己拘束を規範的議論として利用する以上」、持続的統治を困難にする行為をプリコミットメント戦略により事前に聖域化することが妥当であることは「特定の政治的・社会的条件の下で行われた「憲法制定=プリコミットメント」の「良し悪し」を判断できるはず」(109頁以下)だからであり、「ある憲法規定が自己拘束的か否かはその憲法規定が現時点における持続的で討議的な自己統治を促進する装置・技術として説明ないし正当化が可能かという点に依存するとの立場」(111頁)は十分な根拠をもって成立する(らしい)。
つまり、誰が憲法を制定したとしても、ある規定が現世代の「持続的で討議的な自己統治を促進する」ならその憲法制定は自己統治ということである。確かに、ある憲法規定を「現時点における持続的で討議的な自己統治を促進する装置・技術」と捉えるならば、その規定を制定した前世代の意思が現世代の改憲の欲求を阻止することは合理的ではあろう。
愛敬教授のプリコミットメントとしての憲法理解からは、「前世代」を1946年11月3日に生存した日本人だけではなく絶対平和主義と親和性のある憲法価値の創造に寄与した人類史上の総ての人々と読み替えることはおそらくそう困難なことではない。
プリコミットメント論を援用して「現時点における持続的で討議的な自己統治を促進する憲法規定」の聖域化を行い、その聖域を与件として個々の憲法の規定を解釈するという考え方を著者は「憲法解釈の方法としてのプリコミットメント論」と名付ける(111頁)。このように、立憲主義と民主主義の統一体としての実定憲法をこのプリコミットメント論と整合的に再構築する構想を立てて、返す刀で「時代に即した改憲が必要」「改憲は国民主権の発動である」と改憲を迫る改憲派を批判する。
「特定の条項が50年の時代を経て現実と合わなくなった場合、その条項を改正することは当然ありえていい」「この場合、特定の条項がどのような意味で「時代遅れ」になり、……どのような内容の改正が必要か、という実質的な議論をすべきである。「50年前の世代が現代の世代を拘束するのはおかしい」といった類いの一般論は不要である」「このような議論は「プリコミットメント論の立場からみれば、「民主主義の本質を十分に把握していない」、「為にする議論」である」(114頁)。
このプレコミットメント論は、憲法の役割を示すための概念として憲法学を中心に重要な地位を占めつつある。その代表的な論者が、上述の長谷部恭男教授である。つまり、彼によれば「民主国家において、主権者であるはずの人民の政治的な決定権が憲法によって制限されているのも、そうして制限を課された政治権力の方が、長期的に見れば、理性的な範囲内での権力の行使をおこなうことができ、無制限な権力よりも強力な政治権力でありうる」からである(82頁)。民主主義において、権力者もしくは多数派は、権力の誘惑に負けてそれを濫用したり、悪用したりする可能性がある。それゆえに、憲法によって政治権力を事前に制限しておくことで、結果として権力の濫用を防ぎ、長期的な国民の利益の実現を図ることができる。その意味で、このような自己拘束的行動は合理的である。ただしこの文脈では、長谷部教授が国家の貨幣鋳造権の自己拘束と、プレコミットメント論は必然的に結びつくものではない。
しかしながら、ブレコミットメント論も憲法制定の意義を完全に正当化できるわけではない。阪口教授によれば、その理由は大きく分けて以下の3つの理由に分類できる(阪口「テロという危機の時代における『立憲主義』の擁護」川岸編『立憲主義の政治経済学』171-172頁)。
やはり、憲法を制定した人々とその憲法によって制約される人々が同じではない。その上、「憲法典を制定した多数派は、たとえ彼らが後に少数者の地位に転落しても多数者を縛り続けることができる。」
憲法が革命といった体制変動など動乱の状況で制定されることが多いことを考えると、憲法を制定した人々が冷静で合理的な判断を下すことができ、後の世代の人々は日々の政治的駆け引きに惑わされ短期的な利害にもとづいた判断しかできないという考え方は必ずしも正しくはない。
現在の世代が過去の世代に拘束されていることが「自己統治」と言えるのかという問題も、プレコミットメント論では解決されない。
これに対して、Holmesは「積極的立憲主義」という立場から、国民が「立憲主義の制約に従うことで初めて民主主義が創出され、民主主義が安定的に維持される」と説明し、われわれはより良い自己統治を実現するために過去の世代の拘束に従うとしている。
「憲法制定者は単に人民による統治を生み出そうとしたのではなく、……永続的するような人民による統治を生み出そうとした。憲法制定者は、後の世代の人々がそれに続く世代の人々を最大限に拘束することがないようにするために後の世代を最小限に拘束する権限を有していたのである。……このように見れば、マディソン的なブレコミットメントは、原理的に見て民主的でもあり、多数決主義的でもある。すべての将来の多数者に権限を付与するためには、当然、憲法はある特定の多数者の権限を制約しなければならない。したがって、リベラルな憲法は主としてメタ拘束から成り立っている。すなわち、決定する権限を有する者は自らの決定と可能な修正に晒さなければならないというルールと、各世代の人々が後の世代の人々から選択をなす権限を取り上げる能力を制限するルールからリベラルな憲法は成り立っている」(p.162)。
たしかに、Holmesはここではプレコミットメントという用語を使っているが、この箇所はボーダンの説明の章ではなく、アメリカ建国の父たちを取り扱った、その後の章である。したがって、彼が長谷部教授のボーダンの国家の貨幣鋳造権の自己抑制を、その前の章で説明しているとは必ずしも言えないように思われる。ここに、歴史的に遡及した理論上の読み替えがあるのではないか。
Ⅲ.ジャン・ボーダンの国家の貨幣鋳造権の自己抑制
「ヨーロッパでは不安定な王権の下で鋳造権が諸侯に委譲される場合も少なくなく(例えば神聖ローマ帝国の金印勅書では選帝侯に鋳造権を与えている)、貨幣発行利益を確保のためにしばしば額面を水増しした貨幣が発行されて貨幣相場は悪化した。こうした状態が解消されるには、フランスのニコラ・オレームによる『貨幣論』(1355年)における批判(貨幣の新規発行などの操作は、不安定な貨幣価値を安定させる場合にのみ許されるとする)を経て、絶対王政期以後に諸侯の没落に乗じて鋳造権を回収する必要があった。」
貨幣創造についての政府特権の起源
近世初頭に、ジャン・ボーダンが統治権の概念を発展させたとき、彼は貨幣鋳造権(right of coin-age)を統治権の最も重要かつ本質的な部分として取り扱っている。
この特権は最初から、それが公衆にとって利益であるという理由で主張され認められたものではない。それは単に政府の権力の本質的な要素として主張され認められたのである。
金属の重量と純度についての政府証明
政府が引き受けてもよいと了解されていた任務というのは、もとより最初は、貨幣を造りだすというよりも、広く貨幣として役立っていた素材---これはずっと昔から三つの金属、すなわち、金、銀、そして銅だけであったが---の重量と純度を証明するということにあったのである。これは均一の度量衡を確立し証明する任務とやや似たものと思われていたのである。
金属片はそれらが特定の権威者の刻印をもつときにのみ正式の貨幣とみなされたのである。そしてこの権威者の義務は、鋳貨にその価値を与えるために、鋳貨が正式の重量と純度をもっていることを証明することにあると考えられていたのである。
しかしながら、中世の時代に貨幣に価値を与えるのは政府の行為であるという迷信が生まれた。経験がつねにそうでないことを示していたにもかかわらず、この valor impositus(君主により決定された価値)という教義は、主として法律上の教義によって受けつがれ、それはより少ない貴金属の量を含んでいる鋳貨に、同一の価値を付与しようとする君主たちのいつも変わらぬむなしい無駄な試みを正当化するのにある程度は役立ったのである。(今世紀の初めにこの中世的教義はドイツのクナップ教授によって復活させられた。彼の『貨幣国定論』はいまなお現代の法理論にかなりの影響を与えているように思えるのである)。
民間企業がもし許されていたならば、良質でかつ少なくとも信頼に足る鋳貨を供給することができたであろうということを疑う理由はない。事実それは時に行われたのであり、あるいはまた行われるように政府によって権限が与えられていたのである。けれども均一でかつ識別可能な銭貨を供給するという技術上の任務が、いぜんとして重大な困難を示すものであるかぎり、それは少なくとも政府が行う有用な任務であったのである。残念なことに、政府は、少なくとも政府の提供する貨幣を人々が使用する以外に道がないかぎり、この任務は有用であるだけでなくまた大いに有利になされうることにすぐに気付いたのである。貨幣発行特権(seignorage)、すなわち、採鉱費用を償うために課せられる手数料は大変に魅力ある収入源であることが分かり、そしてそれはすぐに鋳貨を製造する費用をはるかに越えて増額されたのである。そしてまた新しい貨幣を鋳造するために政府の造幣所で余分な金属を保有しつづけるということから、次のことが実施されるようになるまでにはほんの一歩にすぎなかった。それは、流通している鋳貨をより少ない金・銀の含有量をもつ各種の呼称の貨幣に改鋳するために回収するということで、中世の時代にますます広まっていったのである。われわれはこれらの価値低下の結果について次章で考察することにしたい。しかし貨幣発行にかかわる政府の機能がもはやある金属片の重量および純度を単に証明するという機能ではなく、発行されるべき貨幣量を計画的に決定することを含むようになって以来、政府はこの任務に全く不適当なものとなったのである。そして無条件にいえることであるが、政府は絶え間なくまたいたるところで信頼を乱用し人々を欺いてきたのである。
ジャン・ボダンの「国家論」からの主権というものの定義なんですが、ジャン・ボダンは十六世紀のフランスの法律家なんですが、既に十三世紀からフランスにおいて使われていた主権という言葉を正確に初めて定義した人というふうに知られております。主権と我々が日本語で訳すこの言葉のもとの意味は、端的に最高の力という意味でして、それをこのジャン・ボダンの「国家論」は最初にフランス語で書かれておりまして、それが十年ぐらい後にラテン語訳になるんですが、その二つのフランス語版とラテン語版においてボダンはちょっと違う定義づけをしております。まず、最初にフランス語版の方では、「主権とは国家の絶対的で永続的な権力である。」というふうに定義しております。これは、今我々がいわゆる国家主権として習っているそういう概念なんです。
今の例えば公民の教科書でも、国家主権とそれから国民主権というときの主権とはページも四十ページぐらいかけ離れたところで説明しております。我々自身、全く同じ主権だという意識なしにこの言葉を使っているんですが、この主権という概念の定義の出発点においては、これは本当に一つの同じ事柄の二つの側面という形で定義されている。これも一つ、我々が心の片隅にとめておくべきことではないかと思います。
殊に、国家主権という言葉が、現在では何かまるでこの言葉を言うこと自体が好戦的な姿勢であるかのようなそんな風潮も見られるんですが、実はボダンの国家主権の定義というのはこれと同時にこんなことを言っております。主権国家というのは、ヨーロッパだけに主権国家があるんではない、アフリカにもアジアにも多くの主権国家があって、これは神の前ではみんな平等の国家なんだという国家平等論をうたっているんです。これはキリスト教の神を前提としているということはあるんですが、考え方それ自体としては二十世紀の国連の基本としている考え方そのままなんですね。そういう先駆的な思想というものが既に主権という言葉に伴ってあらわれていたということも、ちょっと我々がついでながら心しておいていいことではないかと思うんです。
いわゆる君主主権と言われるのがこの後半の定義なんですが、まずここで、ボダンは一体何でこういう定義づけをしたんだろうかということを理解しておく必要があります。これは、今ちらっと申しましたように、フランスの十六世紀というのは、宗教戦争で国内の内紛が絶えない、ほとんど国が分裂するんではないかと内側にいる人にとっては感じられるような、そういう危機の時代でございました。この危機を何とかして乗り切っていくためには、このフランスという国家の船を沈没させないようにしっかりと国家のシステムをつくり上げる必要がある。それにはまず、平たく言えば国が一つの国家としてしっかりとまとまること、それからそのかじ取りをだれがするのかということがしっかり定まっていて、しかもそのかじ取りが自由に行えるようになっていること、これが危機に際しては非常に必要なことである、これがボダンの「国家論」を書くに当たっての心構えだったわけです。
そういう観点から、君主主権の定義というものも行われております。ここには、「主権とは市民や臣民に対して最高で、法律の拘束をうけない権力である。」という、こういう定義づけがなされております。ボダン自身としては、これは今申し上げましたように、あくまでも危機を乗り切るために必要な方便という、そういう意味での定義づけをしているわけです。
ですけれども、皆さんすぐお気づきのように、これはある意味で大変危険なものを含んでおります。法律の拘束を受けない権力というものを主権者に与えた場合に、これは何でも主権者が望めば法律お構いなしに行うことができるという一種の暴君容認論になりかねないわけです。ボダンは、これについては非常にはっきりと歯どめをかけております。ボダンはこの「国家論」の中で、主権の定義と同時に正しい統治論というものを掲げておりまして、主権者といえども、つまり最高の力の持ち主といえどもこの宇宙の絶対の支配者である神に対してはしもべである。神の命令、すなわち正しい統治を行えという命令に背いたらば、たちまち天罰が下るということを言っているんです。
正しい統治というのは何なのかというと、これは彼の言うところによれば、国民の自由と財産と生命を守り保障するということなんですね。つまり、端的に言えば国民のための政治をせよと、こういう縛りがある。それに背いたときには君主、最高の権力者といえども神罰を得ずにはいられないという、そういう考え方なんです。ですから、差し当たってボダン自身の主権論の中では、これは決して闘争的な概念でもなければ暴君容認論でもない。ただし、今申し上げたように、そういう歯どめを抜きにしたらば非常に危ういというものが確かにその中にはあったわけです。
(2001.04.18 参議院憲法調査会)
Ⅳ.結びにかえて
(追記)
ちなみに、夕食は近くのセブン-イレブンで直巻おむすび(とり五目)、3種類の魚介シーフードドリアおよびお~お茶濃い味を買ってきて(640円)、それを部屋で食べて過ごす。